行政書士試験の勉強方法!スケジュールの立て方やノートの取り方!
更新日:2019年3月15日

- 勉強スケジュールを立てるコツは、「いきなり詳細なスケジュールを作り込むのではなく、大きなところから考える」ことです。
- 「時間がない」の対処法として、まず大事なのは、時間を「作る」という自身の意識です。
- ノートの取り方で大事なのは、ノートを取ることで満足してしまうのではなく、ノートを使い倒す、という姿勢です。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
合格を目指す勉強法とは
行政書士試験に合格するには、ある程度まとまった勉強時間が必要です。だいたい600~700時間は必要と言われているので、期間にすると半年から1年くらいは勉強を継続することとなります。
半年先、1年先のゴールを見失わないためにはスケジュールが大事です。そして、スケジュールは作るだけではなく、定期的に見直して現在地とゴールを確認しましょう。
そのとき比べるのは、過去の自分と今の自分です。スケジュール通りに勉強が進んでいるか、出来なかった問題が出来るようになってきているか、それらを過去の時点と比較して、足りない部分を補うようスケジュールを組み直します。
このページでは、スケジュールの立て方と、振り返りに重要なツールであるノートの取り方を中心に、勉強法をご紹介します。
スケジュールの立て方
半年、月、日、時間へと細分化していく
初めて資格の勉強をする人にとっては、スケジュールを立てることも難しく感じるでしょう。コツは、「いきなり詳細なスケジュールを作り込むのではなく、大きなところから考える」ことです。例えば、試験まで半年あるとしたら、まずは、半年で行うことを大まかに決めます。
| 1カ月 |
|
|---|---|
| 2カ月~3カ月 |
|
| 4カ月 |
|
| 5カ月 |
|
| 6カ月 |
|
このように、おおざっぱに行うことを決めます。この時、本試験からさかのぼって考えると分かりやすいです。
次に、その予定を1カ月の予定に落とし込みます。
| 1カ月 | 1日(月) | 憲法 |
|---|---|---|
| 2日(火) | 憲法 | |
| 3日(水) | 憲法 | |
| 4日(木) | 憲法 | |
| 5日(金) | 憲法 | |
| 6日(土) | 憲法 | |
| 7日(日) | 憲法 | |
| 8日(月) | 民法 | |
| … | … | |
| 31日(水) | 民法 |
それから、1日の予定を考えます。
憲法
|
大きなところから始めて、だんだん詳細なスケジュールにしていけば、それほど難しくありません。毎日のスケジュールは、進捗状況に合わせて1週間ごとくらいに見直して、全体が遅れないように調整していく必要があります。
スケジュールは逆算で立てる
スケジュールを立てるときに非常に大事なのが、「逆算」という考え方です。逆算の考え方とは、最初にゴールを設定してそこまでの間に使える時間を計算し、その時間の中でやりくりする、という考え方です。
試験は日程が決まっているので、逆算で考えなくてはなりません。「何となく始めて全部の勉強が終わったとき」が偶然試験日になるということはまずないでしょう。
ですから、まずは試験日から逆算して自分にどれくらい時間があるのかを確認します。そして、その時間の中で勉強を仕上げるには1日どれくらい勉強しなければならないか、どれくらいのスピード感で勉強しなければならないかを計算する必要があります。
また、人によって勉強スピードも理解度も違うので、「1日3時間勉強すれば間に合う」など、一律に決められるものではありません。同じ範囲を勉強するにも、4時間かかる人もいれば2時間で終わる人もいます。自分のペースを把握した上で、スケジュールを立てましょう。
「時間がない」の対処法

時間は「作る」もの
「勉強する時間がない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。確かに、仕事をしながら、家事をしながらですと一日があっという間に終わってしまい、なかなか勉強の時間が取れないと思います。
しかし、「時間がない」からではなく、大事なのは、時間を「作る」という自身の意識です。
試しに、自分の1日の行動を書きだしてみましょう。何をしているでもない時間、何をしていたか思い出せないような時間が結構あるのではないでしょうか。その時間は、全て勉強時間にあてがうことができます。問題は、どうやってその時間を勉強時間にするか、ですが、代表的な方法を2つご紹介したいと思います。移動時間を勉強時間に変える方法と、だらだらしがちな時間を勉強時間に変える方法です。
(1)移動時間を勉強時間に
あるアンケートによると、東京都内に勤める会社員の電車通勤時間は片道平均50分だそうです。往復だと100分ですので、その時間を勉強時間にできれば、毎日確実に100分の勉強をすることができます。
通勤時間は寝てしまったり、何気なくスマホを眺めて過ごしている人が多く見受けられますが、それはとてももったいないことです。とはいえ、満員電車ではテキストを広げるのさえ大変なこともあります。環境としてはあまり望ましくないので、電車内でもできる勉強方法の工夫が必要です。お勧めなのは、
- スマホ一つあればできるe-ラーニング
- 過去問を分冊してコンパクトに持ち歩く
- カードに重要事項をまとめて暗記する
などです。
特に、最近はe―ラーニングの教材がたくさん出ており、満員電車でもテキストを読んだり講義動画を見ることが無理なくできるようになっています。工夫次第で、何気なく過ごしていた時間を全て勉強時間に変えていきましょう。
(2)テレビを見ない
試験までの期間限定で試していただきたいのが、何かを「やめる」ことです。
お酒が好きな人は、毎日の晩酌をやめる。テレビばかり見ている人は、テレビを見ないようにする。趣味や、楽しみをその期間だけ思い切ってやめてみましょう。
そうすると、かなりの時間を確保することができ、その時間が、勉強時間へと変わります。完全に止めるのが辛い人は、頻度をこれまでの半分にすることから始めてみましょう。または、週末だけはいつも通り過ごして良いなど、自分なりのルールを決めるのも一つの方法です。
ただ、すっぱりと完全に止めてしまった方がうまくいく場合もありますので、その期間だけ我慢し試験が終わったらまた思いっきり楽しめば良いのです。
ノートの取り方には3つのステップがある
綺麗なノートはいらない
勉強というと、ノートを綺麗に取ることを考える人も多いのではないでしょうか。しかし、資格試験において綺麗なノートは不要です。なぜなら、資格試験は時間との戦いなので、ノートはその意味通り「メモ」で構いません。
ここからは、合格を意識したノートの取り方について解説していきます。大事なのは、ノートを取ることで満足してしまうのではなく、ノートを使い倒す、という姿勢です。自分で分かれば、他の人には一切読めなくても構いません。
最終的には、ノートが必要なくなることがゴールです。覚えたこと、身に付いたことはどんどん消していって、最後はテキストだけが残ります。そこまでのノートの取りかた3つのステップについて解説します。
(1)科目ごとのノート
ステップ1は、まず科目ごとのノートを用意します。どんなタイプのノートでも構いません。資格の勉強を始めた段階では、気になること、わからないことが山のように出てくるので、科目ごとにノートを作り管理しましょう。科目ごとに分けるメリットは、あとから自分の書き込みを探すのが簡単だからです。この段階で1冊のノートにまとめてしまうと、該当箇所を探すのに時間がかかります。探すための時間は無駄になってしまいます。
書くべきこと
テキストに書いてあることを書き写す必要はありません。書くべきことは、
- 疑問点
- 不明点
- 疑問、不明点に対しての自分の考え
です。
そして、それぞれテキストを読み進めて行くうちに解決するので、解答も一緒に書いておきましょう。
(2)1冊にまとめるノート
ステップ2でノートを仕上げていきます。ステップ1のノートは、勉強が進むにつれて書き込んでいた多くの疑問が解消されていき不要になってくるでしょう。
しかし、中には勘違いしやすい点や、重要なメモも含まれているはずです。それらは、1冊のノートに転記し、なおかつ、新たに出てきた疑問点なども、書き込んでおきます。
この段階まで来ると、疑問点も少なくなってきているので、1冊にまとめておくことで、「テキストとこのノートだけ見れば良い」という状態にすることができます。これはとても大切なことで、外出先、移動中などの勉強にも活用しやすいでしょう。
(3)テキストに書き込んでノートを手放す
ステップ3でノートを手放します。重要なメモは、テキストにどんどん書き込んで、情報をテキストに集約しましょう。これは、本試験会場に持って行くものを厳選するための準備でもあります。本試験会場には、自分で書き込みをしてカスタマイズしたテキストだけ持って行くのが望ましいです。
あれもこれもと持って行っても、結局全てを見ることはできません。テキスト1冊に絞り込んで、直前まで情報を叩き込むのが良いでしょう。テキストに書き込むことにためらいがある人は、大判の付箋に書いて該当ページに貼り、消せるボールペンを使うなどして、工夫してみて下さい。もう覚えたことをあえて書く必要はありません。自分で「忘れそうだな」「これは大事だな」と思ったものだけ書き込めば良いのです。綺麗なノートやテキストよりも、よほど役に立ってくれるでしょう。
行政書士最短合格なら通信講座がベスト
最も効率的に難しい行政書士試験を突破する方法は、通信講座を選ぶことです。その理由は具体的に説明しましょう。
➀過密スケジュールの中でも、自分に合ったスピードで学べる通信講座は、場所や時間に縛られることなく、いつでもどこでも勉強可能で、移動中だけでなく、家事の合間や仕事の休憩時間にも学習を進めることができます。どんなに忙しい人でも、自身の生活パターンに合わせて勉強を続けられます。
②費用が抑えられる通学講座の場合、まとまった授業料に加え、通学のための交通費もかかります。この点、通信講座なら受講料もリーズナブルで、交通費も不要です。
③サポート体制の面で優れています。独学での勉強では解決が難しい疑問点も、通信講座ではサポート体制がしっかりと整っているため、気軽に質問でき、スムーズに勉強を続けることが可能です。不安を感じることなく学びを深めることができます。
フォーサイトの行政書士通信講座の特徴
高合格率が魅力のフォーサイト提供の行政書士通信講座について、その特色を解説します。
①たった4か月で合格!!
行政書士試験の合格までには、一般的に12か月程度の学習期間が必要と言われています。しかしフォーサイトの行政書士講座なら、4か月で合格されている方もいます。
満点主義ではなく、合格点主義で教材を制作しているフォーサイトだから、短期合格が可能なのです。
②不合格だったら、受講料全額返金!!
万一、不合格でも安心!!受講料が全額返金されます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
④講師歴20年以上の実力派講師陣!
フォーサイトの行政書士講座は、福澤繁樹講師・五十嵐康光講師・北川えり子講師、の3名が担当しています。経験豊かな専任講師が、カリキュラムに合わせた講義や教材の執筆を行っています。
⑤「eライブスタディ」は、通信講座でもライブのオンライン講義を受けられる新しい形式です。
自習中心の通信教育では学習ペースが落ちがちですが、定期的なライブ授業に参加することで、学習リズムを一定に保つことが可能になります。
行政書士通信講座を体感するなら資料請求しよう!
もし通信講座が初めて、または以前挑戦したけれど挫折したという方がいれば、新しく通信講座を始めるのに不安を感じることでしょう。そのような不安を少しでも和らげるため、まず資料請求をしてみることをお勧めします。資料請求は無料で行えます。
➀サンプルテキストや問題集に目を通すことで、実際に使われている教材を手に取り、どれほどわかりやすく、学習しやすいかを実感できます。
②無料でeラーニング体験が可能です。
スマートフォンがあれば、場所を選ばずにいつでも学習できるメリットを直接体感することができます。
③合格への近道を示す行政書士試験のノウハウ書が、特別にプレゼントされることになっています。
1分で完了!
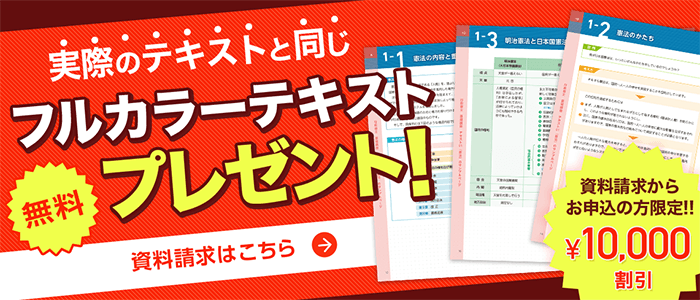
まとめ
スケジュールの立て方、ノートの取り方について、イメージを持ってもらえたでしょうか。どちらも、自分でオリジナルのペース、使い方を作ることが大事です。最初は試行錯誤が必要だと思いますが、時間が経つにつれて自分に合った方法が見つかるはずです。
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















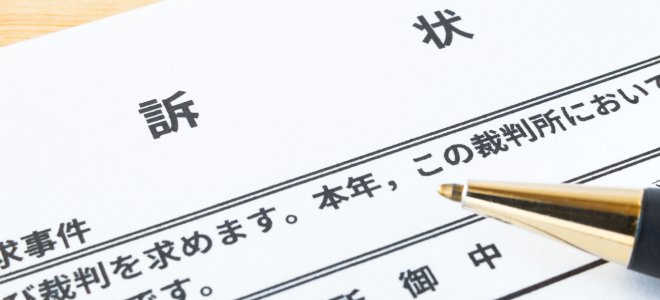


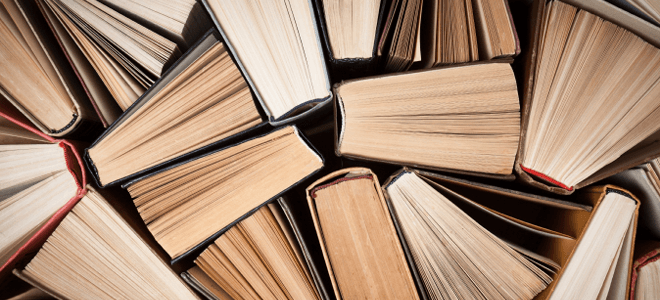



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


