行政書士の平均年収はどのくらい?業務別の年収の違いや年収の高い働き方を紹介
更新日:2023年12月20日
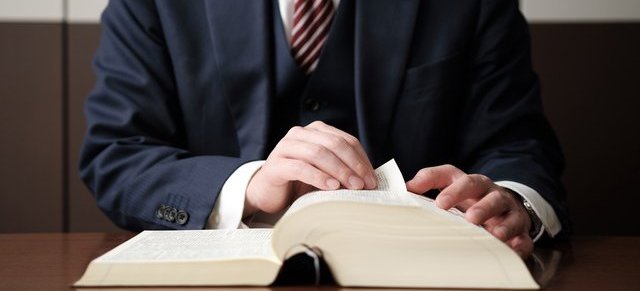
行政書士を目指していて、年収が気になる方もいるでしょう。この職業は働き方によって、年収が大きく異なります。たとえば企業勤務か独立開業かによって、収入が左右されるでしょう。一方で得意とする分野によっても、年収が変わります。
今回は行政書士の収入を知りたい方のため、年収に関する情報をまとめました。収入を上げる働き方も紹介します。以上を踏まえれば、行政書士になったあとの生活を想定できるでしょう。
- 行政書士の仕事は、業務内容によって単価が違います。行政書士として高年収を得るポイントは、申請業務数が多くて単価の高い分野を得意にすることです。
- 行政書士は働き方によって、年収が異なります。兼業や企業勤務、独立開業の3パターンがあり、それぞれ年収の相場が変わります。
- 行政書士として年収を上げるには3つのポイントがあり、積極的な営業やダブルライセンス、高単価業務を得意とすることです。
- 兼業をする行政書士は、複数の業務によって収入を増やせます。そのため収入は約500万円が相場とされ、なかには1000万円を超えることもあります。
- 行政書士になるには「試験合格」が主流ですが、資格要件を満たすことで無資格でなることもあります。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
行政書士の平均年収は?
行政書士の平均年収について、公的な統計調査はありません。インターネットにある収入関連の情報は信憑性に欠ける場合があるので、参考程度にとどめましょう。実際の行政書士は、業務ごとの単価や働き方などの違いにより、年収に差があります。平均年収に関する情報を、以下で見ていきましょう。
平均年収の統計調査はされていない
行政書士の平均年収について、公的な統計調査は見られません。公的機関による収入の調査には、国税庁の「民間給与実態統計調査」や厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」などがあります。しかしこうした機関は、行政書士に限った収入調査をしていません。企業や法律事務所、独立開業などにより働き方が多様化しており、適切な調査が難しいからでしょう。
一方で、民間組織やインターネットユーザーなどによる収入の独自調査が見られます。しかし信憑性の高い公的調査と違い、民間組織だとリサーチの仕方も大きく異なり、信憑性に欠ける場合もあります。そのため民間のデータは、参考程度にとどめてください。
行政書士の収入に関して、公的なデータはありません。信頼性の高い公的機関からの調査がなく、民間企業の調査は不正確な場合があります。行政書士は独立開業や企業勤務などさまざまな働き方があるため、ライフスタイル次第で収入が変わるでしょう。
業務ごとに単価が異なる
行政書士の仕事は、業務内容によって単価が違います。主要な業務は行政手続きですが、その種類は多岐にわたるのが特徴です。手続きの種類によって、もらえる単価が違います。高単価の案件を多く引き受けるほど、年収が多くなるしくみです。
行政書士の収入相場がわかりにくいのは、業務内容の多さが要因でしょう。日本行政書士会連合会の「令和2年度報酬額統計調査の結果」では、400以上もの行政手続きについて、報酬のアンケートが行われました。それだけ業務の種類が多く、行政書士の得意分野も多様化しています。得意分野の報酬が安ければ年収は低くなり、高ければ年収が増加するでしょう。
行政書士として高年収を得るポイントは、申請業務数が多くて単価の高い分野を得意にすることです。単価が高ければ、一定数をクリアするだけで収入を増やせます。さらに申請業務数が多いと、単価がそこまで高くなくても、年収を大きくできるかもしれません。以上から行政書士の年収は、その年における実績がカギです。
行政書士として高年収につながる分野には、薬局開設許可や産業廃棄物処理業許可申請、帰化許可申請などがあります。これらは申請業務数が多く、単価が高い分野として期待できます。
たとえば薬局は、高齢化社会により医療の重要性が高まったため、需要が大きいでしょう。また環境を守るために、産業廃棄物の適切な処理も大事です。日本のグローバル化により、帰化許可申請のような外国人関連の手続きも増えるでしょう。行政書士は、需要が大きくて単価の高い案件をこなせるかで年収が変わります。
働き方によって年収が異なる
行政書士は働き方によって、年収が異なるのも特徴です。独立から間もないときは、それほど収入を得られないでしょう。一方で勤務型は、早い時期からまとまった収入を得られるでしょう。このように日々の働き方によっても、収入に差がつきます。
たとえば独立5年目までは、300万円~400万円が相場でしょう。自力で個人事務所を開業した場合、最初は案件の獲得に苦労します。経営や営業のノウハウを覚えなければならず、軌道に乗るまで時間がかかるからです。このような背景から、独立したあとは収入が限られる可能性に気をつけてください。
一方で行政書士として企業や法律事務所などで勤務する場合、早い時期から高年収を期待できます。相場にして約500万円~700万円を見込めるのです。経営が軌道に乗っている法人で働くため、収入が高水準で安定する可能性があります。以上から行政書士の資格を取って、すぐにまとまった年収を得たい場合は、就職がおすすめです。
勤務型でも独立型でも、10年以上続けると収入が安定します。勤務型は労働環境になじんでおり、一定の案件数を取り続けられます。独立開業の場合でも、10年以上運営している行政書士は、一定のノウハウを実践できているでしょう。いかなる状況でも行政書士を10年続けていれば、高水準の収入を望めます。行政書士は、基本的に働き方によって年収が異なるのが特徴です。しかし10年以上の継続により、収入の安定を期待できるでしょう。
行政書士は食えないからやめとけと言われる理由やメリットについて解説|CHOOSENER
行政書士の働き方による年収の違い
行政書士は働き方によって、年収が異なります。兼業や企業勤務、独立開業の3パターンがあり、それぞれ年収の相場が変わるでしょう。以下で相場をチェックしてください。
| 働き方 | 年収相場 |
| 兼業 | 約500万円~ |
| 企業勤務 | 約500万円~700万円 |
| 独立開業 | 約300万円~400万円(5年目まで) |
それぞれの働き方の特徴を踏まえ、年収相場について解説します。
登録のみ
行政書士登録は、行政書士として働くことを前提としてしかできない仕組みになっています。開業の場合には登録時に事務所の現地調査を受けなければなりませんし、勤務行政書士となる場合には勤務先である行政書士又は行政書士法人と取り交わした雇用契約書の写しの提出が必要となります。「行政書士として働く気はないけれど、とりあえず登録だけ」ということができない以上、「登録のみ」の場合の年収を想定することは不可能なのです。
兼業(税理士や社労士など)
行政書士によっては、税理士や社労士などと兼業する方もいます。このようなダブルライセンスによって、高収入を得る方もいるのです。以上から約500万円の収入が想定され、1000万円を超えるケースもあるでしょう。士業には相談業務や行政手続きなど、相関性のある職業が多いといえます。以上から兼業がうまくいけば、収入アップにつなげられるのです。
たとえば税理士の資格があれば、行政書士としての書類手続き代行だけでなく、税金に関するアドバイスで顧客を助けられるでしょう。社労士にも書類作成代行や相談業務などがあるため、行政書士の立場も兼ねて事業者のトータルサポートが可能です。ダブルライセンスのある行政書士は、もう一方の資格の知識を生かしながら、独自の業務内容を構築できます。
兼業をする行政書士は、複数の業務によって収入を増やせます。ダブルライセンスがあれば、もう一方の知識を味方につけ、多くの顧客のニーズに対応できるでしょう。そのため収入は約500万円が相場とされ、なかには1000万円を超えることもあります。
勤務行政書士
企業勤務では、約500万円~700万円の収入が相場です。主に行政書士事務所や一般の会社への就職などが想定されます。ほかの職業と同じく企業に雇われることで、安定した収入を得られるでしょう。サラリーマンと似た勤務形態で、法律の知識を生かした業務ができます。
企業に就職すれば、行政書士の知識により重要な人材と見てもらえるでしょう。法律や行政手続きなどのサポートを期待されるからです。行政書士の有資格者がそれに応えれば、長期的な勤務につながり、収入を安定させられます。企業勤務では、法律や行政手続きなどの専門知識が強みとなり、人材として高評価をもらえるでしょう。以上から経験が浅くても、一定の収入を期待できます。
独立開業(行政書士専業)
独立開業した行政書士は、5年目以内だと約300万円~400万円の年収が想定されます。経営が軌道に乗れば高収入を狙えますが、それまでは年収が限られるでしょう。開業後は顧客の獲得に苦労するからです。営業だけでなく経営のノウハウを得るにも時間がかかります。
以上から独立した行政書士によっては、年収が100万円程度になることもあります。案件の少ない状態が続くと、収入を上げられないからです。開業直後は知名度が低く、信頼の獲得に苦労するでしょう。独立開業後の行政書士は、案件の獲得や経営のコツをつかむのに時間がかかるかもしれません。年収も5年目までは、約300万円~400万円が相場でしょう。
行政書士の業務による年収の違い
行政書士の年収は、業務によっても異なります。特定業務に専念した場合の年収相場は、以下のとおりです。
| 業務 | 年収相場 |
| 契約書作成 | 約720万円~960万円(年商) |
| 官公署提出書類の作成、提出代行 | 約720万円 |
| 相談業務 | 約240万円 |
実際の行政書士は複数の業務をこなすことになるので、働き方次第で年収は変わるでしょう。そのため以上の表は参考程度にとどめてください。それでも契約書や官公署提出書類のように、専門的な業務が多いほど年収が高くなります。以上を踏まえて、業務ごとの年収相場について見ていきましょう。
契約書作成
契約書作成では、約720万円~960万円の年商を想定できます。あくまでも年商なので、そこから諸経費を引いた分が行政書士の手取りです。それでも不動産売買やビジネスに関する諸手続きをサポートすれば、一定の収入を得られます。案件によっては高単価もあり、高収入に結びつくでしょう。
多くの書類作成業務は、個人だけでなく法人のサポートにもなるので、単価が高い傾向です。一般的には平均3~4万円ほどの書類作成を1日1件こなせば、月20日で約60万円~80万円程度を売り上げられます。そこから経費を引いた金額が、行政書士がもらえる収入です。
契約書には土地や建物などの権利、事実証明、協議内容など多岐にわたります。人々の生活に関わる重要な書類なので、作成や提出の代行が多いほど高収入でしょう。
官公署提出書類の作成、提出代行
官公署提出書類の作成、提出代行は約720万円が年収相場になります。こうした書類には店舗の開業やビジネス上の許可など、重要な案件が多いからです。行政書士がサポートすることで、個人だけでなく法人を助けられます。とくに法人からの依頼は社会的に重要なので、高単価もあるでしょう。
行政書士は手続きの面で事業者をサポートして、高収入を目指せる職業です。たとえば飲食店の事業者は開業の許認可申請から始まり、営業を続ける過程でもさまざまな手続きを求められるでしょう。彼らは仕事で忙しくて書類作成の時間を取れないことがあるので、行政書士のサポートは社会的に重要です。以上から重要書類の作成や提出の代行は案件次第で単価が高く、年収の向上につながるでしょう。
相談業務
相談業務が仕事の中心だと、年収相場は約240万円です。主に行政手続きに関するコンサルティングをします。しかし行政書士以外の独占業務に関する相談は受けられません。以上の制約も、相談業務による収入の低さにつながっています。
一般的に相談業務は行政書士以外の有資格者も行うので、顧客がつきにくいのです。相談だけでなく、書類作成の代行もできないと、高収入を期待できないでしょう。そのため行政書士として出世するには重要書類の作成や、案件獲得に関するノウハウを勉強しなければなりません。
行政書士には相談業務もありますが、それだけでは多くの収入を望みにくいのです。収入を増やすには、書類作成代行のような専門的な業務もこなしましょう。
他資格との年収の違いは?
ここでは行政書士と他資格との年収の違いを紹介します。社労士や税理士、司法書士を比較対象とするので、どの資格を取るべきか迷っている方は参考にしましょう。
社労士
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」にある月間給与の中位数を12カ月分計算した結果、社労士の年収相場は男性が402万8400円、女性が322万9200円です。以上から平均が362万8800円になります。以上から勤務型の行政書士の方が、年収が高い傾向です。
勤務型の年収相場は約500万円~700万円になります。社労士以上に専門的な業務を受けやすく、即戦力として期待されるでしょう。企業や法律事務所などで雇われる場合、行政書士の方が資格としての価値を生かしやすいのです。
行政書士は勤務型であれば、社労士より稼ぎやすいといえます。独立開業直後だと行政書士の方が勤務型社労士より少ないでしょう。しかし多くの案件を獲得していけば、高収入を期待できます。
関連記事:
社労士の年収の詳細はこちら
税理士
税理士のみの年収相場はわかっていません。しかし厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」にある月間給与の中位数を12カ月分計算した結果、公認会計士との合算による平均年収は男性が488万4000円、女性が311万2800円です。平均額は399万8400円でした。以上から行政書士との比較では、独立型だと税理士より低いといえますが、勤務型なら上回る可能性があります。
税理士は所得税や法人など、税金に関するトータルサポートに特化した職業です。一方で行政書士は契約書や官公署提出書類などが対象なので、業務が幅広いといえます。対応できる業務の広さから、収入の高さが想定されるのです。税理士は税の専門家として社会貢献できますが、行政書士は幅広い業務を扱う分、高収入につなげやすいでしょう。
司法書士
厚生労働省の「jobtag」によると、司法書士の平均年収は全国で971万4000円です。行政書士を上回る可能性が高いといえます。司法書士は行政書士と専門性が違い、それが高収入につながっているようです。勤務型でも独立型でも、司法書士の方が収入相場が高いといえます。
司法書士は行政書士より重要な案件を引き受けやすく、収入を上げやすいでしょう。登記や供託など、法的手続きの代行が主な業務です。一方で行政書士による契約書や官公署提出書類の作成代行は、事務や行政上の手続きというイメージが強いといえます。専門性の違いによって、行政書士は司法書士より年収が限られる可能性があるのです。
関連記事:
司法書士の年収の詳細はこちら
行政書士が年収の高い働き方をするには?
行政書士として年収を上げるには、3つのポイントがあります。積極的な営業やダブルライセンス、高単価業務を得意とすることです。以下で詳細を見ていけば、行政書士として出世するヒントがわかります。
積極的に営業する
最初のポイントは、積極的な営業です。とくに独立開業後は、自社の名前を売らなければなりません。さらに営業の円滑化のため、メインの顧客層を想定し、そうした方のニーズにかなう運営を心がけましょう。以上によって、年収の向上を期待できます。
行政書士になりたてのころは、積極的な行動を心がけてください。相手に存在を知ってもらわないと、信頼関係を結べないからです。とくに独立や開業を見据える場合は、積極的なアピールを心がけてください。顧客の相談を受けたときは、相手の気持ちに寄り添い、最善の解決策を出しましょう。誠意のある対応で、顧客の信頼を勝ち取れます。
営業を成功させるには、自身の強みを作りましょう。メインの顧客層を想定し、そうした方の問題と、解決方法を見つけ出しましょう。以上を実践すれば顧客を増やし、収入の増加につなげられます。行政書士として成功するには、自分の名前を知ってもらう努力が大切です。自身の強みを生かした戦略で、顧客との信頼関係を築けます。
ダブルライセンスで幅広い業務に対応する
資格を生かしたキャリアアップの方法に、ダブルライセンスがあります。2つの資格をただ持っているだけでなく、バランスよく生かしながら働くことが大事です。行政書士と関係のある資格なら、ダブルライセンスのアドバンテージを生かせるでしょう。2つの資格を生かせば、兼業によって年収アップを期待できます。
行政書士と相性のよい資格には社労士や宅建士などがあります。社労士と行政書士の共通点は、書類作成代行や相談業務があることです。そのため事業者を中心に、幅広い案件をこなせます。一方で宅建士は不動産取引のサポートが可能です。宅建士の立場から不動産取引に関するアドバイスをしつつ、行政書士の立場から必要な手続きをサポートできます。このようにダブルライセンスがあれば、独自の働き方で収入を上げるチャンスです。
高単価の業務を得意とする
行政書士として年収を上げるには、高単価の業務を得意にしましょう。単価の高い仕事を多数こなせば、収入を増やせます。高単価案件の種類を知り、業務に役立ててください。
たとえば高単価が期待できる案件として、建設業許可申請が挙げられます。日本行政書士会連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」によると、個人による知事への建設業許可申請は、平均報酬額が12万0458円でした。さらに建設業の許可は毎年更新しなければならないので、リピーターの増加にも期待できます。以上からこの分野を得意になれば、継続的な仕事で収入を得られるでしょう。
また外国人の手続きに関する業務も、高収入につながりやすいといえます。たとえば在留資格認定証明書交付申請は、居住資格だと平均報酬額が11万2372円、就労資格だと11万3881円です。ほかにも平均報酬額が10万円を超える案件があるので、日本行政書士会連合会の報酬額統計調査をもとに、やりたい業務を決めましょう。高単価案件を多く手がければ、高収入を望めます。
行政書士が年収アップするために必要なことは?
行政書士の年収アップでは、さまざまな努力が必要です。専門性を極めたり、社会的に新しい分野を学んだりなどの知的好奇心を求められるでしょう。さまざまな人から相談を受ける以上、コミュニケーション能力の向上も欠かせません。年収アップに必要な要素を、以下で3つ紹介します。
専門性を磨く
行政書士としての活躍には、専門性が欠かせません。専門分野をアピールできれば、顧客からの信頼を得やすいといえます。好きなジャンルがあれば、それに関する知識を使って、顧客の問題を解決できるでしょう。以上から行政書士の勉強だけでなく、業務に関する分野の学習も欠かせません。
社会が求める人材は、インターネットで得られるような知識しかない人よりも、高度な知識を有する人です。行政書士の資格試験のテキストや、特定分野を掘り下げた本を多く読み、知識をたくわえましょう。以上を実践すれば、行政書士としての業務を全うしつつ、知識を生かした働き方ができます。高収入を得るなら、行政書士資格を得たあとも特定分野を極めましょう。日々の勉強によって、専門性を極められます。
新分野の知識
新しい分野の知識を得れば、行政書士として活躍できる可能性があります。社会情勢の変化によって、新しいジャンルが生まれるでしょう。そこを強みとすれば、競争相手の少ない分野で活躍できます。近年はドローンや民泊などの業界で、行政書士の需要が見込まれます。たとえば2015年の航空法改正により、ドローンの飛行に一定の制限が加わりました。飛行場所によっては地方航空局への届出が必要なので、行政書士への相談件数が増えるでしょう。
また民泊は近年、新しい宿泊形態として注目されていますが、実際にビジネス化するにはさまざまな手続きが必要です。このように新しい分野を得意とすれば、行政書士として多くの案件を受け入れられるでしょう。
コミュニケーション能力
行政書士として活躍するには、コミュニケーション能力も大事です。職場内での同僚や上司との意思疎通で欠かせません。さらに相談業務や書類作成手続き代行では、顧客とのコミュニケーションが大切です。意思疎通ができないと、いかなる知識があっても仕事がうまくいきません。
そこで伝える力と聞く力を意識してください。伝える力は、自分の伝えたいことを相手にわかりやすく伝えることです。相手を混乱させないように、簡潔かつ明快に言葉を発しましょう。また聞く力は相手の言葉をしっかり聞き取り、理解する能力です。とくに顧客から相談を受けた場合は、聞く力で問題の全容を知り、適切な解決策を伝えましょう。このようにコミュニケーション能力は、行政書士としての活躍に欠かせません。
行政書士になるには
行政書士になるためには行政書士会への登録・入会が必要ですが、大前提として、行政書士になるための資格要件を満たさなければなりません。具体的な方法としては「試験合格」が主流ですが、無試験で行政書士の資格要件を満たす方法もあります。
関連記事:
社労士の受験資格の詳細はこちら
行政書士試験に合格する
行政書士になるための資格要件を満たす方法としては、「行政書士試験合格」が王道です。行政書士試験は「行政書士の業務に関し必要な法令等(法令等科目)」「行政書士の業務に関連する一般知識等(一般知識科目)」の知識が問われる試験です。法令等科目として憲法、行政法、民法、商法、基礎法学、一般知識等として政治・経済・社会、情報通信、個人情報保護、文章理解に関わる出題があり、法令等科目で5割以上、一般知識科目で4割以上、総合得点で6割以上の得点率が合格基準となっています。年齢や性別、学歴等に関係なく、誰でも受験でき、法律系国家資格の登竜門として高い人気を誇る行政書士試験ですが、合格率10%前後の狭き門となっています。
関連記事:
行政書士の試験の詳細はこちら
行政書士の要件を満たす
一方で、行政書士試験合格以外にも、行政書士となるための資格要件を満たす方法が2つあります。まず挙げられる要件は、「公務員として、もしくは特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員・職員として行政事務に20年間(高卒以上は17年間)従事した者」です。長年、行政事務に携わった元公務員等の転職・退職に伴う行政書士開業は比較的多く見受けられ、登録者全体の15%以上を占めます。また、「弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかとなる資格を有する者」にも、行政書士となる資格が与えられます。行政書士資格だけでなく、他資格とのダブルライセンスによって活躍の幅を広げれば、さらなる年収アップが期待できそうです。
まとめ
行政書士の年収相場は勤務型が約500万円~700万円、独立型は5年目までだと約300万円~400万円です。契約書や官公署提出書類など、重要書類の作成を多く受けるほど年収が上がります。
年収を上げるには、専門性の獲得やコミュニケーション能力の向上などが必要です。独立開業後は経営や営業のノウハウも身につけなければなりません。行政書士として高収入を目指すには独自の強みを見出し、顧客との信頼関係を重ねることが大事です。得意分野を生かしながら、キャリアプランを考えましょう。
行政書士 最短合格なら通信講座がベスト
最も効率的に難しい行政書士試験を突破する方法は、通信講座を選ぶことです。その理由は具体的に説明しましょう。
➀過密スケジュールの中でも、自分に合ったスピードで学べる
通信講座は、場所や時間に縛られることなく、いつでもどこでも勉強可能で、移動中だけでなく、家事の合間や仕事の休憩時間にも学習を進めることができます。どんなに忙しい人でも、自身の生活パターンに合わせて勉強を続けられます。
②学習費用を節約できます。
通学講座では、高額な授業料のほかにも通学にかかる交通費が必要ですが、通信講座を選べば、受講料がお手頃であり、交通費が一切かかりません。
③学習サポートが手厚いです。
一人で市販の教材を使って勉強する際には、自分で疑問点を解決しなければなりませんが、通信講座では質問対応をはじめとする充実したサポートが受けられます。これにより、不明な点を放置せず、安心して学習を進めることができます。
フォーサイトの行政書士 通信講座の特徴
ここでは、高合格率で知られるフォーサイトの行政書士通信講座の主な特徴をご紹介します。
➀わずか4ヶ月での合格実績あり!
通常、行政書士試験の合格には約12ヶ月の準備期間が見込まれますが、フォーサイトのコースを受講すれば、4ヶ月で合格することが可能です。この短期間での成功は、フォーサイトが合格点を目指した教材作りに注力しているからこそ実現できます。
②合格できなかった場合でも心配無用です!
受講料は全額戻ってきます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
④フォーサイトの行政書士講座は、講師歴20年以上を誇る福澤繁樹先生、五十嵐康光先生、北川えり子先生の実力派の講師陣によって運営
これら経験豊富な教師たちが、講座のカリキュラムに沿った質の高い授業や教材を提供しています。
⑤通信講座でありながら、ライブ配信の授業が受けられる「eライブスタディ」
周期的に実施されるライブ配信講義のことです。一般的に通信講座は独学が基本ですが、このシステムを利用することで、授業のペースを保ちやすくなり、学習進度の遅れを防ぐことができます。
行政書士 通信講座を体感するなら資料請求しよう!
もし通信講座が初めて、または以前挑戦したけれど挫折したという方がいれば、新しく通信講座を始めるのに不安を感じることでしょう。そのような不安を少しでも和らげるため、まず資料請求をしてみることをお勧めします。資料請求は無料で行えます。
資料請求をすることで、次のような体験が可能になります。
➀サンプルテキストや問題集を閲覧することで、実際の教材の内容を直接確かめることができます。これにより、教材がどの程度理解しやすく、勉強に適しているかを自分自身で体感することが可能です。
②無料でeラーニングを試してみることができます。 この機会を利用して、スマートフォン一台があれば、時間や場所を選ばずに学習できる便利さを実感してみてください。
③行政書士試験を最短でクリアするためのコツをまとめたノウハウ本が、プレゼントとしてもらえます。
1分で完了!
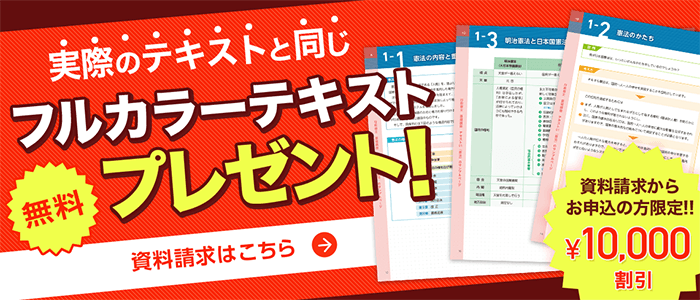
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















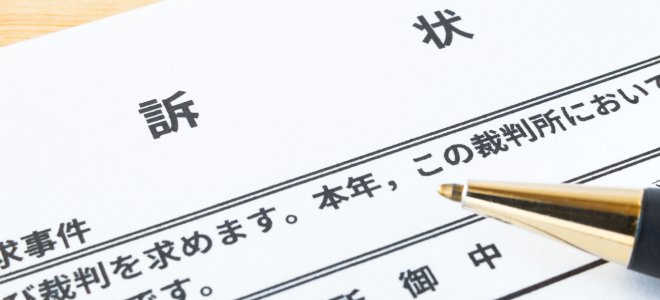


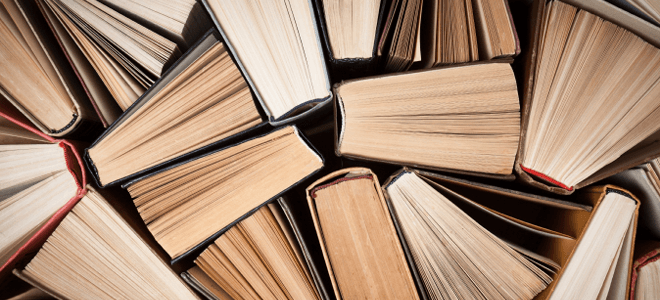



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


