社労士の平均年収はいくら?働き方などの条件別の事例から年収の上げ方まで解説
更新日:2024年6月20日
社労士(社会保険労務士)は、どの程度の年収を獲得できるのでしょうか?
社労士は、企業に勤める、あるいは、自分で事務所を立ち上げて仕事する場合があり、企業勤務型と独立開業型によって年収が違います。 また、社労士として働いてきた就業年数、地域や性別によっても平均年収が異なります。
そこで本記事では、社労士の年収がどのくらいなのか、あらゆる観点からご紹介します。 さらに、社労士の仕事内容を確認して、社労士が年収をアップするためにはどのような方法があるかにも目を向けます。
加えて、社労士になるための方法と社労士の資格合格を目指すためにおすすめの通信講座についてもご紹介します。
- 社労士の平均年収は、全国平均で780万9000円です。
- 社労士の年収は、企業に勤務する場合と、独立開業する場合と、働き方によって異なります。
- 社労士の年収は、就業年数や地域、男女によっても異なります。
- 社労士が年収をアップする方法には、営業スキルを磨くことや幅広い人脈を持つこと、さらに得意分野を持つことなどがあります。
- 社労士になるためには、社労士試験に合格して国家資格を取得しなければなりません。
フォーサイト小野賢一のご紹介
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう。そうすることで、少しずつ実力が身につきます。
社労士試験に合格することで、「なりたい自分」になれます。「なりたい自分」をめざして頑張りましょう!
社労士の平均年収は?
社労士(社会保険労務士)は、企業の労務管理の専門家です。
事業主(企業や個人)に雇用されて働く従業員のために、労働保険や社会保険などの制度があり、業務中に負傷、疾病に見舞われたり、失業したときにも、従業員の生活を守ることができます。
また、従業員が良い環境で働けるように、労働基準や安全衛生といった法律もあります。 事業主(企業や個人)は、このような法律に従って、年金事務所、労働基準監督署などに各種申請書や届出書、報告書を提出しなければなりません。
そのような場面で、社労士は労務管理の専門家として、行政機関への書類提出や手続きを行います。 社労士の年収は、厚生労働省の職業情報サイト「jobtag」によると、全国平均で780万9000円です。

社労士の働き方による年収の違い
社労士には、企業に務めるケースと、自分で開業して仕事をするケースが考えられ、それぞれの働き方によって年収は異なります。
企業に務める企業勤務型社労士は、安定的に収入があって年収も一定額を期待できるでしょう。
一方、自ら起業する独立開業型社労士は、勤務型よりも年収が高くなる可能性もありますが、低くなる可能性もあり、年収の幅が大きいです。
| 働き方 | 年収相場 |
|---|---|
| 勤務型社労士 | 約780万円前後 |
| 独立開業型社労士 | 約100万円~3000万円 |
企業勤務型社労士の平均年収
企業勤務型とは、企業の社員として所属しながら社労士としての業務にあたる働き方です。 勤務している企業から受け取る給料が年収となります。
一般的に人事部や総務部に配属され、社内の従業員の労務管理や労働相談を受ける業務を担います。
仕事の内容は所属する企業によって異なりますが、給与計算、社会保険の手続き、年末調整、退職金の計算などを行うほか、社内で労務に関するトラブルがあれば、その対応を行うこともあるでしょう。
そのような企業勤務型社労士の平均年収は、令和4年度「賃金構造基本統計調査」によると、780万8600円です。企業勤務型社労士は、平均年収が高めであって、さらに一定の収入があることや福利厚生が安定していることがメリットです。
独立開業型社労士の平均年収
一方、自分で事務所を作って社労士としての仕事を行うのが独立開業型社労士という働き方です。 顧客となる企業から依頼を受け、労務管理業務を請け負います。
具体的な業務内容は、依頼を受けた企業の従業員の給与計算、社会保険の手続き、年末調整といったものです。 企業勤務型は、その企業に所属する従業員の一人となるため、安定して給与を受け取ることができますが、独立開業型の場合は顧客から依頼を受けて初めて収入を得られます。
そのため、自ら顧客を見つけるべく営業活動を行う必要があり、社労士としての経験や人脈、さらに、経営のためのスキルも求められます。
社労士のうち、独立開業型の公的データがないため、平均年収がいくらになるのか正確な数字は未知数です。 しかし、顧客の信頼を得て多数のクライアントを持っている場合、年収はかなり高くなり、3000万円を超えることも十分考えられます。
しかし、開業したばかりなど、顧客が少ない時期は、年収が数百万円台になることも可能性として考えられます。
条件別社労士の平均年収
社労士の年収は、社労士として勤務している年数、さらに地域や男女によっても異なります。令和4年度の賃金構造基本統計調査のデータから、そのような条件によって社労士の年収がどのくらい異なるのかを見てみましょう。
【就業年数別】社労士の平均年収
まずは就業年数別の年収を見てみましょう。近年では薄れつつありますが、日本では古くから年齢が高く経験を積んだ人の方が年収が高い傾向があります。その傾向は、社労士についても同じであることがわかります。
| 就業年数 | 平均年収 |
|---|---|
| 0年 | 557万3000円 |
| 1〜4年 | 662万7800円 |
| 5〜9年 | 705万7200円 |
| 10〜14年 | 823万4800円 |
| 15年〜 | 1052万8500円 |
社労士としての就業年数が多くなるほど、平均年収は高くなっていきます。
ただし、企業の役員に就くような場合、社労士としての業績以外にも、その他の評価指標で認められている可能性もあります。
しかし、就業年数が増えれば増えるほど、年収がアップするという傾向はうかがえます。
【地域別】社労士の平均年収
次に地域別の平均年収について見てみましょう。主な都道府県別に社労士の平均年収をまとめたのが下記の表です。
| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 853万6100円 |
| 大阪府 | 635万5300円 |
| 愛知県 | 568万8700円 |
| 島根県 | 450万9400円 |
| 高知県 | 452万4700円 |
| 鳥取県 | 356万8300円 |
平均年収が最も高いのは東京都で、大阪府や愛知県などの都市部では年収が高いことがわかります。 しかし、地方では年収が低くなり、東京都と比べると半分以下になることもあります。
社労士の顧客となるのは企業が主であるため、企業の数が多いエリアほど、多くの顧客を獲得できます。
また都市部の企業は売上も大きいことから、社労士に支払われる費用も高額になる傾向にあります。
そのため、社労士として高い収入を得たい場合は、地方よりも都市部で働くことを検討するのもおすすめです。
【男女別】社労士の平均年収
最後に男女別の平均年収を見てみましょう。
| 性別 | 平均年収 |
|---|---|
| 男性 | 851万5100円 |
| 女性 | 603万7400円 |
平均年収は、女性よりも男性の方が高く、250万円ほどの差がついていることがわかります。月収で考えると15〜20万円程度の差があると考えられます。
男女でこれだけ大きな差があるのは、男性の方が役職者が多く、それだけ年収が高くなっていることがひとつの理由でしょう。
女性は、妊娠や出産などによって、一時的に社労士としての仕事から離れることも考えられるため、就業年数が男性よりも短くなることもあり得るでしょう。 また、子育てや介護などを理由に、時間を短縮して働いている場合も考えられます。
昔は男女で収入に大きな差がありましたが、現在は女性の活躍を後押しするような社会の流れができています。 しかし、実際には男女の年収の差が生まれていることがうかがえます。
さまざまな働き方が認められるようになり、女性も活躍できる社会になってきているため、少しずつこの男女差が埋まっていくことが期待できるのではないでしょうか。
社労士の仕事内容とは
ここで社労士の仕事がどんな内容なのか確認しましょう。社労士の主な業務は「労働及び社会保険に関する書類の作成および手続き代行」「事務代理」「労働関係紛争の代理」「帳簿書類の作成」の4つがあります。
「労働及び社会保険に関する書類の作成および手続き代行」は、社会保険労務士法の「1号業務」にあたるものです。
労働保険、社会保険、雇用保険などに関して、行政機関に提出する書類を作成し申請を行います。 例えば、企業に新入社員が入社すれば被保険者資格取得届を、退職すれば社会保険の資格喪失届などが必要になります。
「事務代理」は、給与計算や人事雇用と労務に関する相談などが当てはまります。 「労働関係紛争の代理」は、賃金未払いや不当解雇、パワハラなどの問題を解決する役割を担います。
そして最後の「帳簿書類の作成」は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の整備・管理・保管を行う内容です。 これらは労働基準法にもとづいたもので、法律が改正されればそれにあわせて、管理する必要があります。
関連記事:
社労士とは?試験概要や仕事内容から資格を取得するメリット、なるための方法まで解説
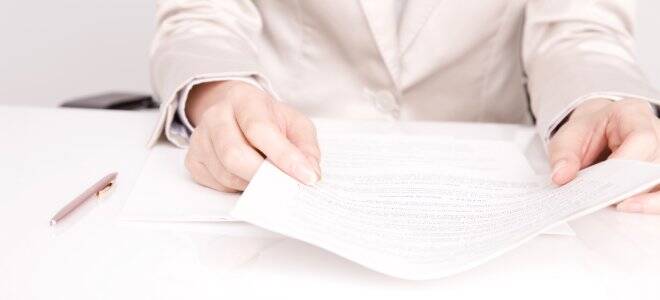
社労士が年収をアップする方法は?
社労士として働きながら、年収をアップするには、どのような方法が考えられるでしょうか? ここでは主に、社労士として独立したときにできる方法を考えてみましょう。
ポイントとなるのは、営業スキルを磨くこと、幅広い人脈を作ること、そして、自分の得意分野を持つことです。
営業に関するスキルを磨く
社労士としての年収を上げるには、まず多くの顧客を獲得して、多くの案件をこなす必要があります。 新規顧客を増やしていくためには、自らを売り込む営業活動が必須です。
新規顧客の開拓は決して簡単なことではありませんが、社労士の仕事は、一度企業から依頼を受けたのち、問題なく仕事を継続できている限り、そのまま長期間契約が続きやすいという特徴があります。そのため、新規顧客を増やしていくことが、年収アップに直結しやすくなるのです。
営業といっても、企業に片っ端から電話をかけたり、知らないオフィスに訪問する古いスタイルよりも、自身や自分の事務所のWebサイトを見やすく作り、問い合わせにも真摯に対応することが大切です。
近年はSNSを利用して新規顧客を開拓するという方法も有効でしょう。
幅広い人脈を持つ
自分でビジネスを起こすには、どのような業界であっても幅広い人脈があればあるほど心強いでしょう。
自分の直接の知人ではなくても、知り合いの知り合いを紹介され、そこから新しく顧客となってくれる人と出会う可能性もあります。
とくに独立開業したばかりの時期は、顧客数も限られているため、経営が厳しい状態になるかもしれません。そのようなときに人脈があれば、顧客創出のきっかけとなる人が現れて、力になってくれるでしょう。
幅広い人脈があることで、社労士として活躍している人とも繋がることが出来るかもしれません。 同業者との出会いは、仕事の参考になることはもちろん、社労士としての経営のヒントがもたらされることも期待できます。
自分の得意分野を持つ
自分の得意分野を持つことも、とても大切です。社労士として取り扱う仕事は多岐にわたるため、その中で得意な分野を極めてもいいでしょう。
また、社労士はあらゆる業界の企業から仕事を依頼される可能性があり、どのような業界においても、従業員を雇用する企業にとって、社労士が必要とされているのは大きなメリットです。
しかし、それぞれの業界には特有の習慣や事情もあるでしょう。それらをよく理解して対応できる社労士はとても重宝され、評価が上がるでしょう。
このように、得意な分野や業界を持つことで社労士としての価値を高め、結果として、年収アップにもつながることが期待できるのです。
社労士になるにはまずは資格取得を目指そう
社労士になるためには、国家試験である社労士試験に合格しなければいけません。社労士試験は1年に1度しか行われておらず、合格率は5〜6%前後とかなりの難関です。
そのため、何年もかけて、何度も受験して、やっと社労士試験に合格する人も少なくありません。
社労士試験の受験資格は、「短大や大卒、高等専門学校卒以上」または「3年以上の実務経験があること」または「厚生労働大臣が認めた国家試験の合格者」であることです。このどれかに該当すれば受験することができます。
社労士最短合格なら通信講座がベスト
難易度が社労士試験を確実に合格するためには、通信講座を利用するのが最適です。その理由は、まず通信講座が忙しい人に最適だから。
通信講座なら自分自身のペースでどのような環境でも学習が可能になります。通勤時間や自宅での空き時間、仕事の休憩中など、いつでもどこでも勉強ができる柔軟性があり、仕事や家事、育児が忙しくても、各自の生活スタイルに適した学習が実現できます。
また、通信講座は経済的にとってもお得。対面式の講座では、授業料がかかるし、学校に通うための交通費がかかりますが、通信講座では受講料が割安に設定されていて、お財布にとってもやさしいです。
また、学習サポートが充実しているのもうれしいところ。市販のテキストでの自習では、わからないことがあったときに自分で調べて解決しなければなりませんが、通信講座では質問対応や学習アドバイスなど、豊富なサポートが用意されています。
そうしたサポートのおかげで、わからない点を残さずにしっかりと学習を進めることができるんです。
フォーサイトの社労士通信講座の魅力とは?
通信講座のなかでも、とくにおすすめなのがフォーサイト。高い合格率が評判です。社労士試験は1年に1度しか行われていないため、1年間をかけて学習するのが一般的。でもフォーサイトの通信講座を利用すれば、わずか4か月の学習で合格した人もいるんです。
これは、フォーサイトのカリキュラムが、社労士試験に合格するために必要な情報がわかりやすく的確に網羅されている証拠。その結果、短期間での合格が可能なのです。
また、もし試験に落ちてしまっても受講料は全額返金保証されているため、受講料が無駄になるという心配も不要。安心してチャレンジできます。
使用満足度90%というわかりやすいフルカラーテキストと、二神大貴講師・松尾歩美講師・小野賢一講師・加藤光大講師などのベテラン講師陣による指導で、効率的なカリキュラムに沿って勉強できます。
社労士通信講座を体感するなら資料請求しよう!
これまで通信講座の経験がない方や、通信講座を試してみたけれど途中で断念したことのある方は、通信講座を始めるにあたって不安を感じるかもしれません。
そんなときは、まず資料請求から試してみてはどうでしょう?資料請求は無料なので、気軽に利用できるはずです。
しかも、サンプルテキストや問題集に目を通すことができるから、実際に使われている教材のわかりやすさや学習しやすさを実感できます。
また、無料でeラーニング体験も可能。スマートフォンがあれば、場所を選ばずにいつでも学習できるので、ぜひ試してみてメリットを直接体感してみましょう。
おまけに、社労士試験合格の秘訣を集めたノウハウ書を無料でもらえるから、これからの学習のヒントとしても利用できます。
社労士は高い年収を期待できる!
社労士の年収は、全国の給与所得者の平均年収よりも高く、高給が期待できる仕事です。 企業に勤務しながら社労士として働く方法もありますが、独立開業すればさらに年収を上げることも可能でしょう。
もちろん、社労士として年収を高めるためには、営業活動を行ったり、人脈を築いたり、得意分野を作ったりなど、さまざまな努力が欠かせません。そのような創意工夫によって、社労士としての経験と実績を積み、高い年収を目指していきます。
社労士になるためには、難関である社労士試験に合格しなければなりませんから、ぜひ効率的に勉強して、社労士を目指していきませんか?
1分で完了!
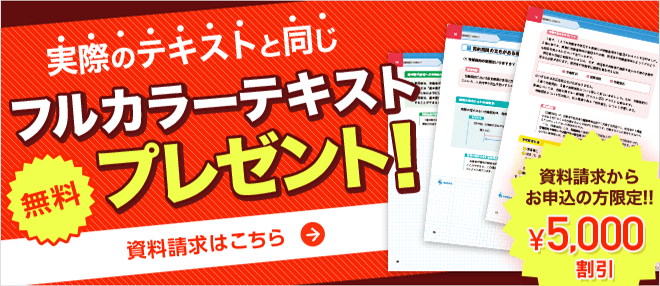
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




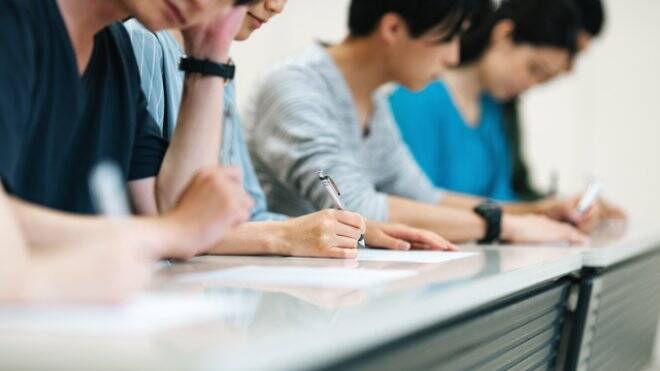


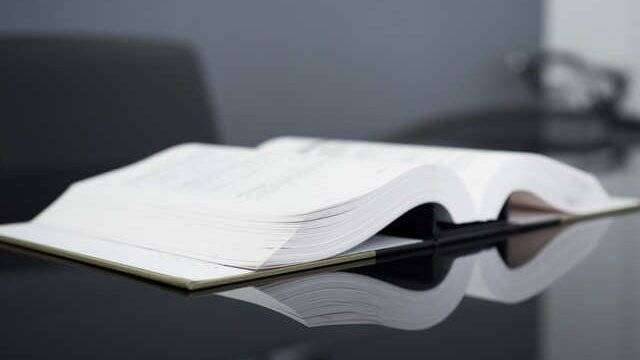









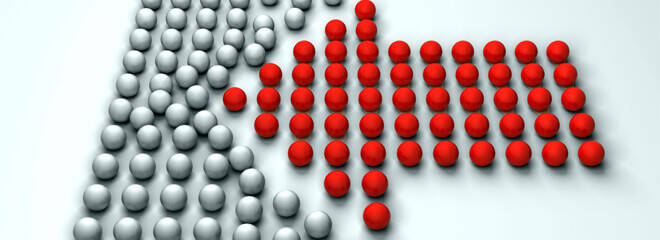
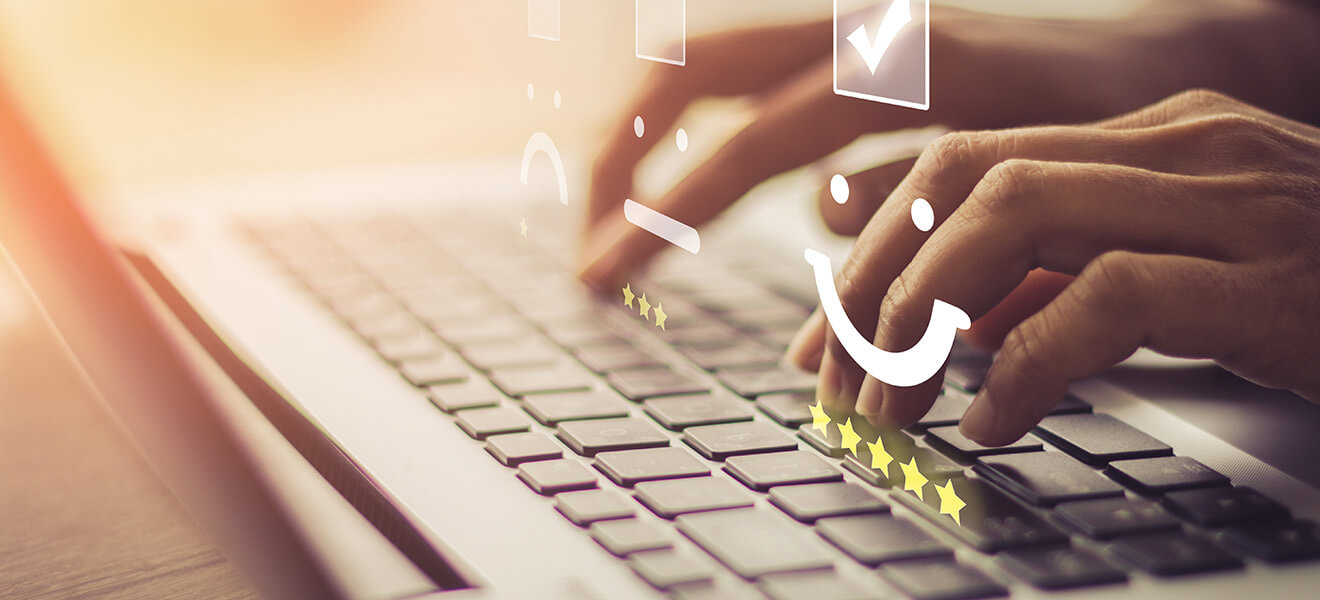





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


