社労士試験・労災保険法「通勤災害」とは?業務災害との違いを区別して得点源に!
更新日:2021年3月15日
社労士試験に出題される労災保険法では、業務災害と併せて「通勤災害」についても問われます。一般的には業務災害も通勤災害も一括りで「労災」と捉えられがちですが、実際にはそれぞれの定義や給付内容が異なり、社労士試験対策としてはしっかり区別して覚えておかなければなりません。
ここでは、社労士試験の労災保険法で問われやすい「通勤災害」の基本を解説します。
社労士試験労災保険法のキーワード「通勤災害」
.jpg)
「労災」というと、仕事中に負ったケガや業務に起因する病気が対象となるイメージです。ところが、労災保険法は、通勤が原因で生じた労働者の負傷、疾病、障害又は死亡についても「通勤災害」として労災保険給付の対象としています。
「通勤災害」認定上、重視される「通勤」の定義
通勤災害の適用の有無を考える上では、労災保険法上の「通勤」を正しく理解することが重要です。
通勤とは、分かりやすくいえば「自宅と会社間の往来」ですが、日々の通勤はこの限りではなく、あらゆるケースが想定されます。この点、労災保険法では「通勤」の定義について、以下のように定めています。
就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(3)については少し分かりにくいですが、典型的なケースとして「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動」があります。
社労士試験の通勤災害関連でおさえるべき「逸脱」「中断」
労災保険法上、「移動の経路を逸脱し又は移動を中断した場合における、逸脱又は中断の間及びその後の移動」は原則として通勤として取り扱いません。
ただし、逸脱又は中断がごく些細な行為である場合はそもそも「逸脱・中断とみなされない」、さらに以下に該当すると認められる場合には「逸脱又は中断の間を除いて」合理的な経路に復した後から通勤と認められます。
✓ 日常生活上必要な行為であり、
✓ 厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合
社労士試験で問われる通勤災害該当事例
.jpg)
通勤途中の逸脱とは「就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路から外れること」を指し、中断は「通勤と関係ない行為を行うこと」です。
原則として、逸脱・中断に該当した時点で原則通勤とみなしませんが、例外もあります。
例えば、「通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する」「経路上の店でタバコやジュースを購入する」といった些細な行為については、通勤経路を逸れても逸脱・中断とみなされないと判断されています。
通勤経路からの逸脱・中断に関わる労災適用の有無の判断については、社労士試験でよく問われるポイントです。過去問等から十分にケーススタディをしておく必要があります。
通勤災害の該当事例「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」とは?
それでは、逸脱・中断に該当するものの、その間を除いて本来の合理的通勤な経路に服した後からは通勤とみなされる「日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」とはどのようなケースなのでしょうか?
厚生労働省で定めるものとして、以下をおさえておきましょう。
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他
これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 - 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
通勤途中でも通勤災害不該当になるケース
一方で、通勤途中で生じた事故であっても、被災者の故意や過失によるものは、原則として通勤災害と認められないと覚えておきましょう。
例えば、「通勤途中で他人と喧嘩をして負傷した」「自宅に戻る途中で飲酒しその後にケガをしたり事故に遭ったりした」等の事例があります。
さらに、「日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」の定義を超えた逸脱・中断についても通勤災害とは認められません。例えば、「自宅とは反対方向の商店で買い物をするための経路で交通事故に遭った」事例は通勤災害とは認められていません。
また、「得意先の忘年会に参加し、18時51分の退社後から23時過ぎまで飲食店をはしごして飲酒し、その後帰宅途中で事故に遭った」事例についても、忘年会自体が社会通念上業務と認められないことから、その後の災害も通勤災害とされませんでした。
このあたりの対策については、過去問を中心に、社労士試験に出やすい事例の検討をされておくと安心です。
社労士試験頻出!通勤災害の保険給付
.jpg)
これまで解説してきた「通勤の定義」「通勤経路の逸脱・中断の判断」「通勤災害の該当・不該当事例」は、社労士試験でよく問われる通勤災害関連の出題ポイントです。
これらに加えてもうひとつ、おさえておくべき点に「通勤災害時の保険給付内容」がありますが、概ね業務災害時と同様のため、あえて明確に区別して学習する必要はありません。通勤災害について、業務災害時の取扱いと異なるポイントのみ、おさえておきましょう。
療養給付
業務災害同様、通勤災害の場合も、治療にかかる療養費は労災保険から給付されます。給付の名称については、業務災害の場合は療養補償給付、通勤災害の場合には療養給付となり、若干異なります。
給付内容について、基本的には業務災害時にも通勤災害時にも違いはありませんが、通勤災害の場合は200円の自己負担額が生じ、これは休業給付から天引きされます。
休業給付
通勤による負傷・疾病の療養のため、仕事に就くことができなくなった従業員に対して、休業給付が支給されます。業務災害時の休業補償給付と同様の給付です。休業給付の支給要件は、次の通りです。
|
休業開始後4日目から休業が終了、または傷病年金の受給に切り替わるまで支給されます。
業務災害の場合には、休業開始後3日目までは事業主から休業補償が支払われますが、通勤災害の場合には事業主による法的な補償義務はありません。支給金額は1日単位で計算され、原則「平均賃金の60%」ですが、一部労務可能な場合には賃金額との差額が支払われることになります。
その他の保険給付
通勤災害の場合にも、業務災害同様、障害給付、遺族給付、傷病年金、介護給付、葬祭料などの保険給付を受けることができます。ただし、通勤災害にかかる労災保険給付では、療養給付や休業給付同様、給付の名称に「補償」の文字が入りません。
まとめ
- 社労士試験の労災保険法で頻出の「通勤災害」については、「通勤の定義」や「逸脱・中断」「通勤災害該当事例・不該当事例」について理解を深めることが大切です
- 労災保険法上、「通勤」とは、「住居と就業の場所との間の往復」「就業の場所から他の就業の場所への移動」「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」に該当するいずれかの移動を、就業に際して合理的な経路及び方法により行うことをいいます
- 通勤経路からの逸脱や通勤の中断については、原則、労災保険法上の通勤からは外れますが、逸脱・中断の程度や事由によっては例外的に通勤とみなされることがあります
- 通勤の逸脱・中断、通勤災害の該当・不該当については、社労士試験で具体事例が出題されることがあるため、十分にケーススタディをこなしておくと安心です
- 通勤災害時の労災保険給付は、業務災害と同様です
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




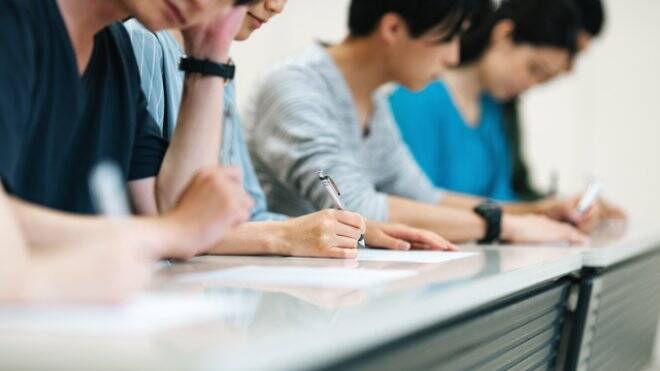


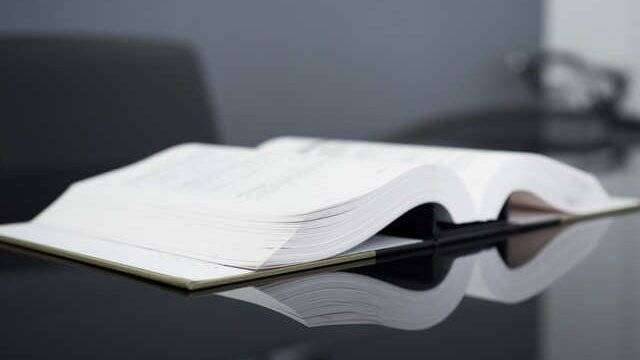









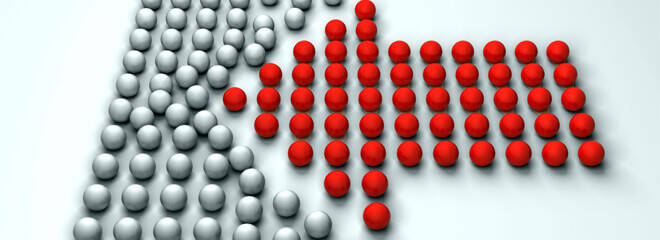
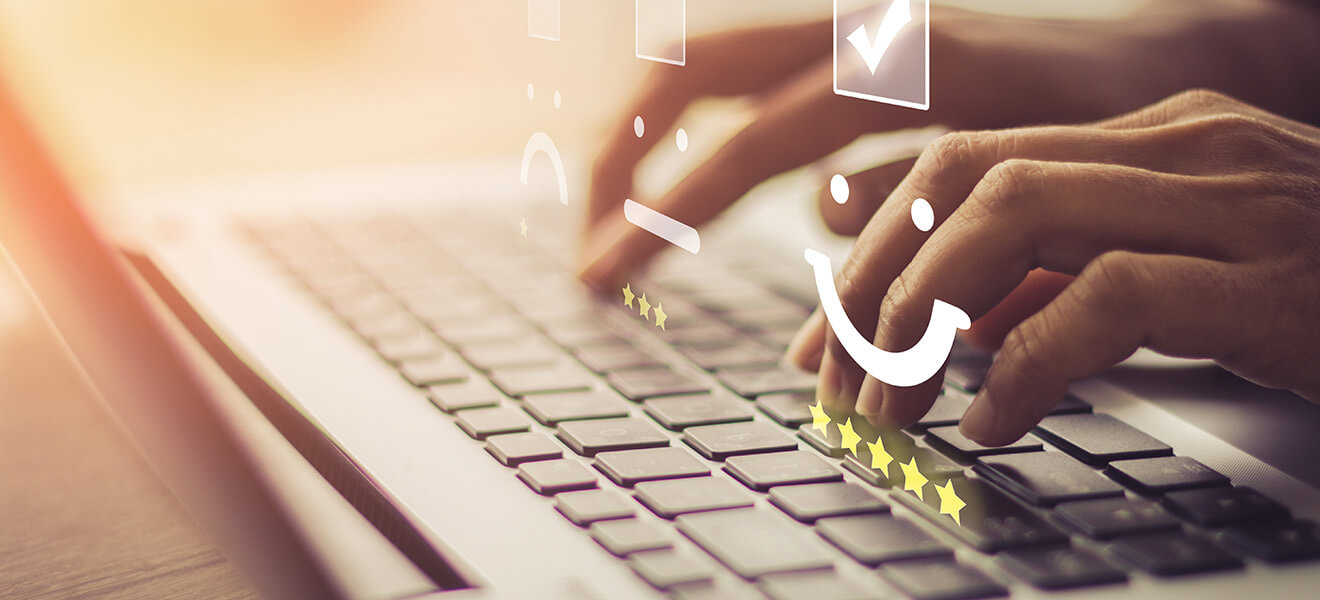





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


