「高年齢求職者給付金」とは?社労士試験出題の観点から解説
更新日:2021年6月7日
雇用保険では、一定の条件を満たす被保険者が離職すると、失業中の再就職支援として基本手当を受給できます。この点、65歳以上の雇用保険被保険者である「高年齢被保険者」は通常の基本手当に代わって「高年齢求職者給付金」を受給することになります。
社労士試験対策上、おさえるべき雇用保険関係の給付金制度のひとつとして、「高年齢求職者給付金」についても例外なくインプットしておきましょう。
高年齢求職者給付金とは?制度の基本を理解しよう

高年齢求職者給付金については、通常の基本手当との比較で理解するのがスムーズです。
ここでは、社労士試験の出題傾向を踏まえ、「受給要件」「給付日数」「基本手当(失業保険)との違い」「計算方法」を確認しておきましょう。
高年齢求職者給付金の受給要件
冒頭でも触れたとおり、高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険被保険者)が離職した後、安心して求職活動に取り組めるように支給される給付金です。
高年齢求職者給付金は、離職した高年齢被保険者が以下の2要件を満たす場合に支給申請できます。
|
✓ 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算します。なお、2020年8月1日以降に離職した人について、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月ない場合、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヵ月として計算します。 ✓ 失業の状態にあること 具体的には、離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。失業中であっても、就職する意思・能力がないと判断される場合、高年齢求職者給付金は支給されません |
高年齢求職者給付金の支給額
高年齢求職者給付金は、被保険者期間に応じて、支給される額が変わります。
・被保険者期間1年未満:30日分の基本手当日額相当
・被保険者期間1年以上:50日分の基本手当日額相当
高年齢求職者給付金額の算出については後述しますが、一般被保険者に支給する基本手当日額が用いられます。
その他、支給を受けることができる期限(受給期限)に定めがあること、待機期間や離職理由による給付制限期間があることも、基本手当同様のルールが適用されます。
高年齢求職者給付金と基本手当との違い
ここで、高年齢求職者給付金と基本手当の相違点をまとめておきましょう。類似制度の違いを明らかにしておくことで、両制度内容を正しくインプットできます。
|
高年齢求職者給付金の計算方法
高年齢求職者給付金は、「基本手当日額×30もしくは50(被保険者期間による)」によって算出します。
基本手当日額は、以下の計算式で導き出すことができます。
| ① 賃金日額を算出 |
|
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計÷180 ただし、賃金日額には上限額(13,700円)と下限額(2,574円)があります。 |
| ② ①で算出した賃金日額に50~80%の給付率を乗じて、基本手当日額を算出 |
|
給付率は、賃金日額が2,574円以上5,030円未満で「80%」、12,390円超13,700円以下で「50%」です。 これに当てはまらない5,030円以上12,390円以下の範囲の場合は、以下に当てはめて算出します。 0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額 |
「高年齢求職者給付金」の社労士試験出題実績

高年齢求職者給付金は、基本手当の原則と照らし合わせながら学ぶことで、比較的内容を理解しやすい制度です。基本的なルールや基本手当との相違についてインプットできたら、過去問演習を通して実際の本試験での問われ方を確認していきましょう。
高年齢求職者給付金の受給期限の延長の有無(平成19年雇用保険法)
以下の選択肢について、正誤を判別する問題です。
「高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。」
回答:×
高年齢求職者給付金の受給期限は「離職の日の翌日から起算して1年を経過する日」であり、基本手当のような受給期限の延長は認められません。
雇用保険給付の国庫負担(平成29年雇用保険法)
以下の選択肢について、正誤を判別する問題です。
「雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。」
回答:〇
国庫負担についても、細かな点とはなりますが、社労士試験対策上おさえておく必要があります。
国庫は、原則として、
- 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)についてはその要する費用の4分の1
- 日雇労働求職者給付金についてはその要する費用の3分の1
- 雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)についてはその要する費用の8分の1
- 広域延長給付を受ける者の係る求職者給付に要する費用の3分の1
- 就職支援法事業として支給する職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
を負担することとしています。
一方で、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、雇用保険二事業については、国庫負担は行われないものとしています。
まとめ
- 社労士試験雇用保険法のキーワードのひとつである「高年齢求職者給付金」は、65歳以上の雇用保険被保険者である「高年齢被保険者」が離職後の求職活動期間中に受給できる給付金です
- 高年齢求職者給付金は、離職した高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険被保険者)が「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること」「失業状態にあること」を受給要件として支給されます
- 高年齢求職者給付金の支給額は被保険者期間に応じて定められており、被保険者期間1年未満で30日分の基本手当日額相当、被保険者期間1年以上で50日分の基本手当日額相当となっています
- 社労士試験対策上、高年齢求職者給付金と基本手当の相違点を意識することで、両制度内容を正しく理解し、本試験で得点につなげやすくなります
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




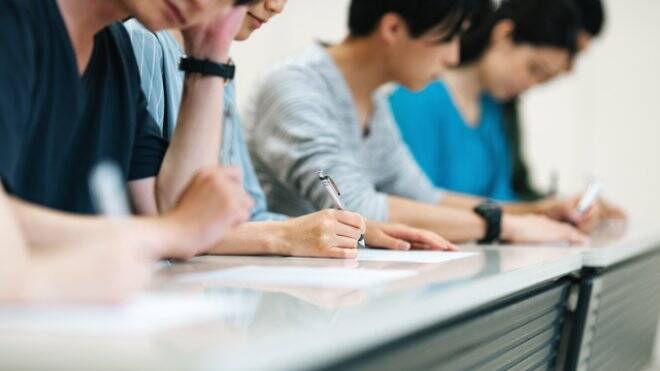


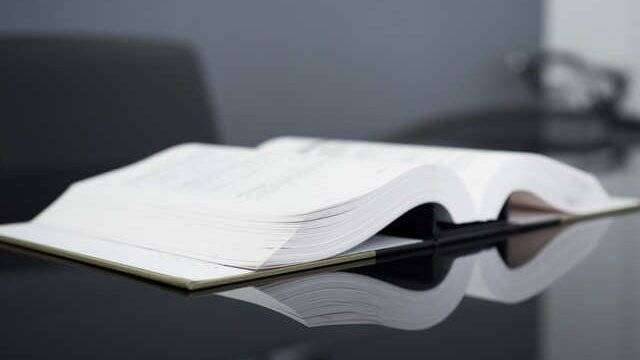









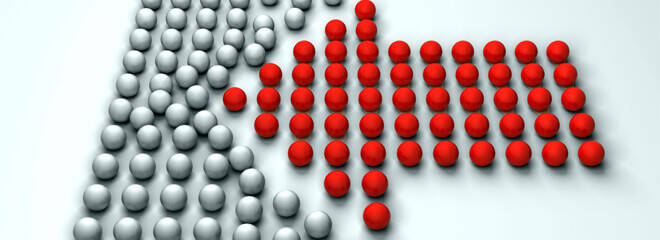
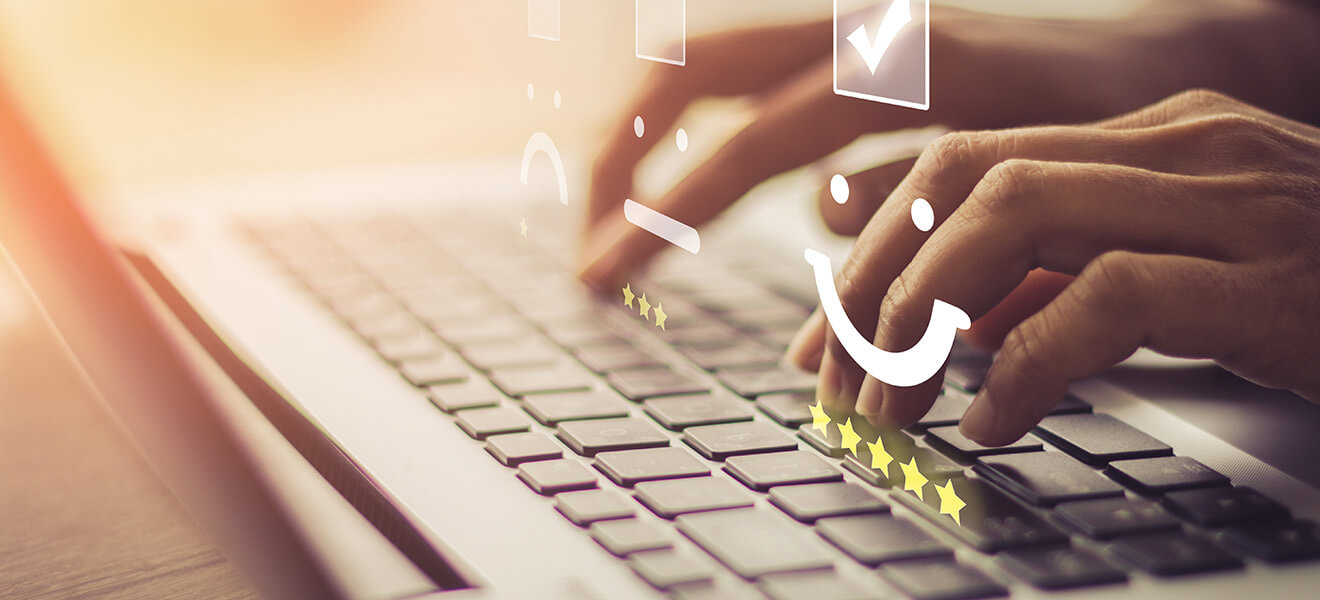





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


