独学で行政書士試験に合格するためのテキストの選び方を徹底解説!
更新日:2019年9月26日
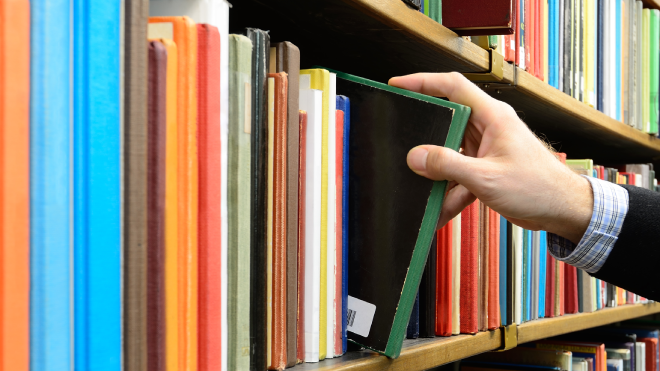
行政書士試験の合格に向けて独学で勉強を始めようと考えている場合に、まず重要となるのは、どのようなテキストや参考書を選ぶか、という点です。
学習にあたって、基本テキスト、過去問題集は必須です。それに加えて、学習の進度に応じて、入門テキストや六法、模擬試験などの活用を検討することになります。
- テキストを選ぶ際は、可能な限り、書店に足を運んで、実際に手に取って見ることがおすすめです。
- 基本テキストは最新版のものを用いるようにしましょう。
- 過去問を解くことは、テキストのインプットと同じくらい、もしくはそれ以上に重要であり、試験勉強においては必須の学習方法です。
- 試験の1ヶ月前までに最低1回は時間を計って模擬試験を実施することがおすすめです。
フォーサイト福澤講師のご紹介
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!
行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。
私といっしょに合格しましょう!
どんなテキストを選ぶべきか?
学習にあたっては、基本的事項が網羅されたテキストを一冊用意しましょう。
可能な限り、書店に足を運んで、実際にページをめくってみることをおすすめします。書店にいくつも並んでいるような基本書であれば、掲載内容にそこまで大きな差はないと考えられますので、「自分にとって使いやすいか」という感覚を大切にしてください。
選ぶ際には、例えば、次のような観点を意識して比較してみるのがよいでしょう。
- ページの色分けがなされており、視覚的に理解しやすいか
- 自分にとって説明が分かりやすいか(同じ項目について解説している箇所を読み比べてみる、というような比較方法が効果的)
- 目次、索引が充実しているか
など。
学習の最初の頃は、一度テキストを使ってみて、合わないなと思ったら別のテキストを買ってみるのも良いと思います。1年間近く用いるテキストですから、勉強しやすいな、と感じることが最も大切です。
初学者は、まず入門書から。
テキストのページをめくってみて、説明が難しいな、と感じた場合には、初学者向けの入門書を一冊読んでみることがおすすめです。
特に、法律を勉強したことのない方にとっては憲法や民法の基本的な考え方をまず理解することで、各科目の学習効率が大きく変わってきます。
専門用語を使わずに、平易な日本語で書かれているため、比較的すぐに読めます。入門書を読むという過程は一見遠回りのようにも感じられますが、効果は非常に大きいです。基本テキストに戻った後の理解のスピードの違いに驚くはずです。
基本テキストは、必ず最新版を使用しよう。
すでに何度か受験していたり、過去に受験した知り合いから教材を譲り受けて勉強したりする、などという場合もあるかもしれません。
そうした場合であっても、基本テキストは最新版のものを用いるようにしましょう。
行政書士試験にはさまざまな法律が登場し、それぞれに法改正があります。
特に、民法はこのたび約120年ぶりとなる抜本的な改正がなされ、2020年4月より施行されます。
民法は他のあらゆる法律の基本ともなるものであり、当然、他の科目にも影響があります。そういった点からも、必ず最新版のテキストで学習を進めましょう。
六法は購入するべき?
行政書士試験において、とりわけ民法や行政法においては、各法律の条文知識が重要となります。条文の「素読」(条文を順に読んでいく方法)も、有効な勉強法であると言われています。
ただし、学習の初めの頃は、まず条文の内容をテキストの解説を読んで理解することが優先です。意味がわからないのに条文を素読しても、効果は低いです。
そのため、六法の購入は、基本テキストや過去問題集に比べて、優先順位は低いです。
重要な条文については、ピックアップして掲載しているテキストも多いので、ひとまずそれで十分でしょう。
過去問題集は必須!
実際の過去問題を解いてみることは、テキストによる基本事項のインプットと同じくらい、もしくはそれ以上に重要であり、試験勉強においては必須の学習方法です。
テキストの内容をいくら完璧に理解しても、それだけでは本番の試験に立ち向かうことはできません。
過去問題を繰り返し解くことで、合格に必要な知識を身につけることはもちろんのこと、出題傾向や設問形式別の解き方を身につけることができます。特に、行政書士試験は3時間という時間制限があり、問題文の中には比較的長い文章も登場しますので、感覚を身につけておくことは非常に重要です。
過去問題は、最低でも過去3年分を解くようにしましょう。学習時間が確保できるのであれば5年分は解いてみるのが望ましいです。
過去問題集を選ぶ際のポイントは、「解説が充実していること」、この一点です。解説部分を読んでみて、わかりやすいと感じたものを選ぶようにしましょう。
なお、年度ごとの過去問題はセンターのホームページから無料で入手することも可能です。(著作権の都合上、掲載されない問題も一部あります。)解説や法改正への対応がないため、実際に学習するには不便ですが、学習のはじめに雰囲気を掴むためには活用してみるのも有効ではないでしょうか。
関連記事:
行政書士の過去問についての詳細はこちら
模試は積極的に活用しよう
市販の模試は2,000円程度で販売されており、2、3回分の模擬試験問題が収録されているため、本番に向けた予行演習を行うにあたってコストパフォーマンスが高いです。
ただし、自分で時間を測って実施しなければならないため、学習が遅れている場合などには後回しにしてしまいがちだというデメリットもあります。
一方で、予備校などが主催する模擬試験は、市販のものよりは高価ですが、会場で実際の試験日と同じスケジュールで受験でき、雰囲気をつかめるというメリットがあります。成績表が発行されるため、受験生内での順位も把握することができます。解説も、市販のものに比べて充実しています。
また、予備校の場合、各社が出題予想を元に問題を作成していることから、本試験における的中率が高い傾向があります。
メリット、デメリットをふまえて、ご自身に合うものを積極的に活用するようにしましょう。試験の1ヶ月前までに最低1回は時間を計って模擬試験を実施し、反省点を元に残り1ヶ月の学習計画を組み立てるのが理想的なスケジュールです。
勉強時間はどれくらい?
行政書士試験合格のために必要な勉強時間は、600時間〜800時間と言われています。
大切なのは、選んだテキストや過去問題集を、一度だけなぞるのではなく、何度も繰り返すことです。
行政書士試験の試験範囲は広いので、他の科目を学習している間にどうしても知識は少しずつ抜けていきます。試験直前になって、数ヶ月前に勉強した範囲を忘れてしまった、というようなことのないように、定期的に復習できるようにしましょう。
例えば、テキストや過去問題集の目次に学習日付をメモしておくだけで、前回の学習日からどれだけ間隔が空いたかを一目で把握することができます。とりわけ独学の場合には、このようなちょっとした工夫が大きなカギを握ります。
勉強時間については、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:
行政書士の勉強時間についての詳細はこちら
行政書士試験最短合格なら通信講座がベスト
難しい行政書士試験に、最短で合格するのにベストの学習法は、ズバリ、通信講座です!
その理由は、下記のとおりです。
➀過密スケジュールの中でも、自分に合ったスピードで学べる
通信講座は、場所や時間に縛られることなく、いつでもどこでも勉強可能で、移動中だけでなく、家事の合間や仕事の休憩時間にも学習を進めることができます。どんなに忙しい人でも、自身の生活パターンに合わせて勉強を続けられます。
②経済的にお得です。
対面式の講座には、授業料とは別に交通費が加わりますが、通信講座では受講料が割安に設定されており、移動のための費用も不要です。
③学習サポートが充実しています。
市販のテキストでの自習では出会った疑問を自分で調べる必要がありますが、通信講座では質問対応や学習アドバイスなど、豊富なサポートが用意されています。そうした支援のおかげで、わからない点を残さずにしっかりと学習を進めることができます。
フォーサイトの行政書士通信講座の特徴
ここでは、高合格率で知られるフォーサイトの行政書士通信講座の主な特徴をご紹介します。
➀たったの4ヶ月で行政書士試験に合格!
一般には1年の学習期間が推奨されますが、フォーサイトの講座を利用すれば、4ヶ月で合格する受講生もいます。フォーサイトは合格を最優先に考えた教材開発を行っており、その結果、短期間での合格が可能になっています。
②不合格に終わっても大丈夫!
受講した費用はしっかり全額返金されます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量、重要情報のカラー分け、理解を深めるイラストが豊富に含まれており、それが高い合格率につながっています!
④講師歴20年以上の実力派講師陣!
フォーサイトの行政書士講座は、福澤繁樹講師・五十嵐康光講師・北川えり子講師、の3名が担当しています。経験豊かな専任講師が、カリキュラムに合わせた講義や教材の執筆を行っています。
⑤通信講座でありながら、ライブ配信の授業が受けられる「eライブスタディ」
周期的に実施されるライブ配信講義のことです。一般的に通信講座は独学が基本ですが、このシステムを利用することで、授業のペースを保ちやすくなり、学習進度の遅れを防ぐことができます。
行政書士通信講座を体感するなら資料請求しよう!
もし通信講座が初めて、または以前挑戦したけれど挫折したという方がいれば、新しく通信講座を始めるのに不安を感じることでしょう。そのような不安を少しでも和らげるため、まず資料請求をしてみることをお勧めします。資料請求は無料で行えます。
資料請求すると、こんな体験ができます。
➀サンプルテキストや問題集を閲覧することで、実際の教材の内容を直接確かめることができます。
これにより、教材がどの程度理解しやすく、勉強に適しているかを自分自身で体感することが可能です。
②無料でeラーニングを試してみることができます。
この機会を利用して、スマートフォン一台があれば、時間や場所を選ばずに学習できる便利さを実感してみてください。
③行政書士試験に最短で合格するためのノウハウ書がブレゼントされます。
1分で完了!
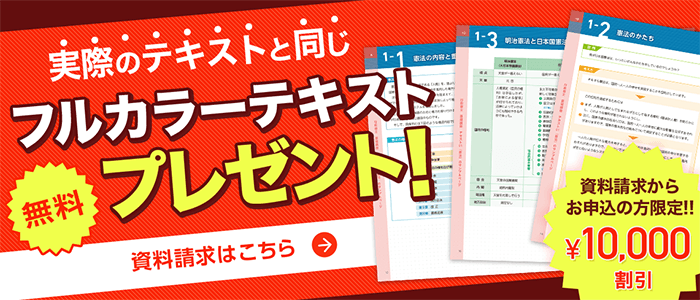
まとめ
独学で行政書士試験を受験する場合であっても、適切なテキストを選んで勉強を続けていけば、合格は十分に狙えます。
何よりも大切なことは、自分に合ったテキストや過去問題集を選ぶこと。そして、選んだ後は、それらを信じて何度も繰り返すことです。試験まで頑張っていきましょう!
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
●フォーサイト講師ブログ
















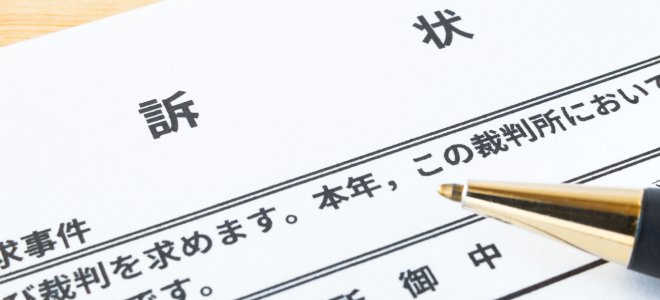


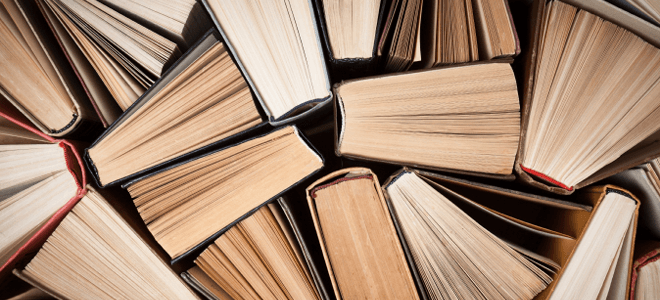



 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


