社労士試験の申し込み方法は?手順から注意点までわかりやすく解説
更新日:2023年12月17日

社労士試験は毎年1度の実施です。
そのため申し込みはしっかり期日内に終わらせ、確実に受験できるようにするのが重要です。
社労士試験の受験には、受験資格の証明書など必要書類がありますので、2024年度試験を受験する予定の方も、2023年のうちにその準備をしておくのがおすすめです。
では2024年度社労士試験のスケジュールはどうなるのか?社労士試験の受験申し込みに関して注意すべきポイントはあるのかなどを紹介していきたいと思います。
ここで紹介する2024年度社労士試験のスケジュールは、この記事執筆時点ではまだ未定のスケジュールであり、例年のスケジュールからの予想でしかありませんので、イメージとして見ていただければと思います。
- 社労士試験の申し込み方法に関しては、2種類の申し込み方法があります。ひとつは郵送による申し込み、もうひとつはインターネットからの申し込みです。
- 社労士試験の顔写真は無背景が条件となりますので、自宅などで撮影する場合は、白い壁の前で撮影する必要があります。
- 社労士試験の受験料は15,000円です。
- 社労士試験の申し込みに当たっては、受験申込書以外に顔写真や受験資格証明書の提出が必要です。
フォーサイト小野賢一のご紹介
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう。そうすることで、少しずつ実力が身につきます。
社労士試験に合格することで、「なりたい自分」になれます。「なりたい自分」をめざして頑張りましょう!
2024年度社労士試験の予想スケジュール
まずは2024年度の社労士試験のスケジュールに関して、現時点で予想できる範囲で紹介していきたいと思います。
2024年度(令和6年度) 社労士試験 予想スケジュール |
|
|---|---|
| 試験案内書請求期間 | 2024年3月1日(金)~5月31日(金) |
| 試験公示 | 2024年4月15日(月) |
| インターネット申し込み期間 | 2024年4月15日(月)10:00~5月31日(金)23:59 |
| 郵送申し込み期間 | 2024年4月15日(月)~5月31日(金)消印有効 |
| 試験日 | 2024年8月25日(日) |
| 合格発表日 | 2024年10月2日(水) |
上の表で紹介しているスケジュールに関しては、あくまでも過去の傾向を参考に予想したスケジュールとなります。正確な日程に関しては、2024年4月に発表される、社労士試験の正式な公示を参考にしてください。
2023年度社労士試験の日程
上で紹介した予想スケジュールの参考になった、2023年度社労士試験のスケジュールを紹介しておきましょう。
2023年度(令和5年度) 社労士試験 スケジュール |
|
|---|---|
| 試験案内書請求期間 | 2023年3月1日(水)~5月31日(水) |
| 試験公示 | 2023年4月17日(月) |
| インターネット申し込み期間 | 2023年4月17日(月)10:00~5月31日(水)23:59 |
| 郵送申し込み期間 | 2023年4月17日(月)~5月31日(水)消印有効 |
| 試験日 | 2023年8月27日(日) |
| 合格発表日 | 2023年10月4日(水) |
2023年度社労士試験の公示は4月の中旬に行われましたが、試験案内の請求は3月からスタートしています。とはいえ、案内書の申請をしたからといってすぐに案内書が届くわけではなく、案内書に関しては公示以降の発送となりますのでご注意ください。
社労士試験の申し込み方法は2種類
社労士試験の申し込み方法に関しては、2種類の申し込み方法があります。ひとつは郵送による申し込み、もうひとつはインターネットからの申し込みです。
将来的にはインターネット経由の申し込みのみとなることが予想されますが、2023年11月の段階で翌年の試験申し込みに関しての発表がありませんので、恐らく2024年度社労士試験も、2つの申し込み方法から選べる形になると予想されます。
それぞれのポイントを簡単に紹介していきましょう。
郵送による申し込み
郵送による申し込みを希望する場合、まずは試験案内の入手が必須となります。社労士試験の試験案内には、社労士試験の申込書や、受験料の払い込み用紙が同封されていますので、これらの用紙を使用して申し込みを行います。
試験案内書の請求は郵送で申し込みます。準備するのは以下の通りです。
- 往信用封筒(長型3号)
- 返信用封筒(角型2号)
- 往信用切手 84円
- 返信用切手 140円
まずは往信用の封筒に請求先の住所を書き込みます。社労士試験の試験案内の請求先は全国で1ヶ所ですので、間違えないようにしましょう。
〒103-8347
東京都中央区日本橋本石町 3-2-12
社会保険労務士会館 5階
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
往信用封筒の表面には、宛先住所以外に「案内書請求」と赤字で明記しましょう。
返信用の封筒には140円分の切手を貼付し、自身の住所と氏名を書き込んでおきます。この返信用封筒を往信用封筒に入れ、ポスト投函すればOKです。
ほかでは、受験料の払い込み方法が、郵便局からの申し込みに限られますので、この点は覚えておいてください。
インターネットからの申し込み
インターネット経由で申し込みを行う場合、「社会保険労務士試験オフィシャルサイト(以下:社労士サイト)」から申し込む形になります。
申し込みの詳しい手順は後に紹介しますが、必要書類の画像データ化などが必要になりますので、事前に準備しておくといいでしょう。
受験料の払い込みは、クレジットカード払いかコンビニ/銀行ATM(Pay-easy)払いとなります。
郵送による申し込み手順
まずは郵送申し込みの手順に関して紹介していきましょう。
- 社労士試験の案内書を入手する
- 申込用紙に必要項目を記入し顔写真を貼付
- 必要書類を用意
- 受験料を払い込む
- 申込用紙・必要書類・受験料払い込み証明書を同封し簡易書留郵便で郵送
簡単に紹介すると、上記の通りの手順で申し込む形になります。申し込みに関しては、封筒の大きさなども決められていますので、詳細は社労士サイトを参考にしていただき、ここでは特に注意すべき点を紹介していきます。
顔写真の要件
社労士試験の申し込みには顔写真の提出が必須となります。これは郵送申し込みでもインターネット申し込みでも同様です。また、写真の要件も原則同じですので、ここで顔写真の要件に関して紹介しておきましょう。
- 縦45mm・幅35mm
- 3ヶ月以内に撮影
- 背景無地&肩より上が写っており、帽子なし・正面向き
- カラー可、白黒可
- 受験時に眼鏡を着用する方は眼鏡着用で撮影
社労士試験に申し込む際の顔写真に関しては、街中にある証明写真を撮影する機械などで撮影してもいいですし、お手持ちのスマホなどで自分で撮影しても問題ありません。
自分で撮影する場合の注意点は特に2つ。背景とピントに関してです。
社労士試験の顔写真は無背景が条件となりますので、自宅などで撮影する場合は、白い壁の前で撮影する必要があります。自宅に無背景の壁が見当たらない場合は、背景に布団のシーツを被せるなどして、無背景の状況を作り出しましょう。
またピントが合っていない顔写真の場合、申し込みが受け付けられない可能性がありますので、しっかりとピントを合わせて、鮮明な画像を撮影するようにしましょう。
画像の加工は原則NGです。社労士試験の顔写真は、受験当日に本人が受験することを確認するための写真です。実際の見た目と写真が違いすぎると、受験ができない可能性もありますのでご注意ください。
受験資格証明書など必要書類を用意する
社労士試験は受験資格のある試験です。また、一部受験科目免除の制度もあるため、この制度を利用する場合は、それを証明する書類の提出も必要になります。
社労士試験の申し込みで必要になる可能性がある書類は以下の通りです。
| 書類 | 提出する必要がある方 |
|---|---|
| 顔写真 | 受験者全員 |
| 受験資格証明書 | |
| 免除資格証明書 | 受験科目の一部免除を申請する方 |
| 特別措置申請書・添付書類 | 特別の措置を申請する方 |
| 戸籍個人事項証明書・住民票等 | 改姓・通称等氏名に関する証明が必要な方 |
| 外字届 | 合格証書における氏名に関して、JIS第二水準該当しない漢字の使用を希望する方 |
必要書類の中には取得に時間がかかるものもあるかと思いますので、こちらも申し込み前に準備しておくといいでしょう。
受験料を払い込む
郵送申し込みの場合は、郵送をする前に受験料を払い込む必要があります。この受験料の払い込みにはひとつ注意点がありますので紹介しておきましょう。
社労士試験に郵送で申し込む場合、受験料の払い込みは郵便局のみとなります。案内書に同封されている払い込み用紙で払い込みを行いますが、このとき必ず郵便局の窓口から申し込んでください。
郵便局のATMからでも払い込み操作自体は可能ですが、ATMで払い込みをしてしまうと、手元に払い込みを証明するものが残りません。払い込みを証明することができなければ、社労士試験に申し込むことができなくなってしまいますので、必ず窓口から払い込み、控えを受け取るようにしましょう。
簡易書留郵便で郵送
申込書への記入、顔写真など必要書類の準備、そして受験料払い込みの控えが揃ったら社労士試験の申し込みが可能になります。
まずは往信用に長型3号の封筒を準備し、その中に準備した書類を入れます。さらに角型2号サイズの返信用封筒に、自宅の住所や氏名を記入し、必要金額の切手を貼付した上で同封してください。
準備できた封書は、ポスト投函ではなく、窓口から簡易書留郵便で郵送してください。
インターネット申し込み手順
続いてインターネットからの申し込み手順を紹介していきましょう。
- 社労士サイトで受験案内を確認
- 社労士サイトでマイページを作成
- 申し込みフォームで必要事項を記入
- 申し込みフォームから必要書類をアップロード
- 受験料の払い込み方法を選択
- 一旦申し込みは仮で完了
- 指定された期日までに受験料を入金
- 入金確認が取れれば申し込み完了
申し込みは自宅のPCから行うようにしてください。社労士試験の申し込みには自宅の住所など多くの個人情報の記入が必要であり、多くの方が触れるPCで申し込みをすると、こうした個人情報が外部に流出する可能性があります。
自宅にPCがない、もしくは通信環境がないという方はスマホからの申し込みも可能です。
マイページの登録は毎年必要
社労士サイトでのマイページ登録に関しては、1年ごとにデータが更新されます。例え昨年受験して、マイページを作成した方でも、試験終了後にはマイページのデータは削除されます。
毎年申し込みのたびにマイページの作成が必要ですので、必ずマイページ登録から始めましょう。
マイページ登録にはメールアドレスが必要です。重要な連絡に関しても、このメールアドレスに届くようになりますので、メールアドレスの受信設定を確認し、迷惑メールなどに紛れ込まないようにしておいてください。
顔写真・必要書類をアップロードする
インターネット経由の申し込みでは、必要書類をアップロードする形になります。アップロード先は指定の申し込みフォームですが、インターネット上で申し込みを行いますので、当然必要書類は画像データ化する必要があります。
| 書類 | 提出できるデータ |
|---|---|
| 顔写真 | JPG,JPEG |
| 受験資格証明書 | JPG,JPEG,PDF |
| 免除資格証明書 | |
| 特別措置申請書・添付書類 | |
| 戸籍個人事項証明書・住民票等 | |
| 外字届 |
画像データ化する際の保存形式は上記の通り。指定された形式で保存しておきましょう。
必要書類を画像データ化する際は、不明瞭な部分がないように注意してください。特に受験資格証明書などの書面を画像データ化する際、スマホなどで撮影する場合は、すべての文字が鮮明に見えるかどうかをチェックする必要があります。
自分で撮影するのが難しい場合は、スキャナでスキャンして画像データ化するのが推奨です。自宅にスキャナがない場合は、コンビニエンスストアの複合機でもスキャンサービスを提供しているケースがありますので、こうしたサービスを利用するのもいいでしょう。
受験料の支払い方法を選択
インターネット申し込みの場合、受験料の払い込み方法はクレジットカード払いかコンビニ/銀行ATM(Pay-easy)払いのどちらかを選ぶ形になります。
クレジットカード払いを選んだ場合は、その場で決済を行います。コンビニ払いを選んだ場合は、申し込み手続き完了後に、コンビニで支払いを行います。
入金確認が取れれば申し込み完了
クレジットカード支払いの場合は、カードの決済が下り次第申し込みは完了します。コンビニ払いの場合、指定された期日までに支払いを行い、その支払いの確認が取れた時点で申し込みは完了となります。
申し込みが完了した際には、最初のマイページ作成時に登録したメールアドレスに申し込み完了メールが届きますので、そのメールの受信を確認できるようにしておきましょう。
社労士試験の注意点
ここまで社労士試験の申し込み手順や、その中で注意すべきポイントなどを紹介してきました。ここからは申し込みだけではなく、社労士試験全体に関する注意点などを紹介していきましょう。
受験料や払い込みに関して
社労士試験の受験料は15,000円です。数ある資格試験の中でもやや高めの受験料となりますので、社労士試験受験を考えている方は準備しておきましょう。
社労士試験の受験料支払いなどの注意点に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は参照してください。
社労士試験の試験形式に関して
社労士試験のポイントとして挙げられるのが試験形式です。試験は1日で完了しますが、ポイントとなるのが試験時間です。
試験は午前と午後に分かれており、午前中の試験時間が80分、午後の試験時間は210分という長丁場の試験となります。もちろん途中退室は原則認められていません。
1日で合計5時間近い試験時間もさることながら、午後は3時間30分休憩なしでの試験となりますので、体調管理が重要になります。
社労士試験を受験する方は、試験勉強はもちろん、試験当日の体調に関しても十分に気を付けましょう。
社労士試験の時間割や各科目、試験方式などに関しては以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:
社労士の試験内容や試験科目について解説
社労士試験の受験資格に関して
社労士試験は受験資格のある試験です。受験資格にはいろいろな決まりがあり、どれか1点でも満たしていれば受験は可能です。
社労士試験の受験資格などの詳細に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
関連記事:
社労士試験の受験資格は大卒だけ?社労士試験の受験資格完全解説
社労士試験の受験地に関して
社労士試験の受験地は日本全国各地に設置されます。2023年試験を例に挙げると、設置されるのは13都道府県。人口の多い都市部に設置される傾向がありますので、受験者の方はその中からどこか好きな受験地を選択して受験する形になります。
受験者が選択できるのは「受験地(都道府県)」までです。東京都などは都内に複数の受験会場が設置されますが、細かな受験会場までは選択できません。
受験地に関しては、年度によって変更になる可能性がありますので、必ず受験案内などで確認してから申し込みましょう。
社労士試験の申し込みは早めに行うのがおすすめ
社労士試験の受験を考えている方は、早めに受験申し込みをするようにしましょう。なぜ早めがいいのかという点に関して、いくつか理由を紹介していきます。
希望の受験地での受験が可能になる可能性が高い
早めの申し込みを推奨する最初の理由は受験地に関してです。
上記の通り、受験者が希望を出せるのは受験地までで、受験会場までは選択できません。また受験会場に関しては先着順で決定し、定員を超えるとその受験会場での受験はできなくなります。
希望の受験地の会場が定員オーバーになると、受験者は希望した受験地ではなく、近隣の受験地の受験会場での受験となります。これで困るのが地方部に住んでいる方でしょう。
例えば山形県の宮城県寄りに住んでいる方で、仙台の試験会場であれば日帰りでも行けるという方がいたとします。こういった方の申し込みが遅れて、仙台会場が定員に達してしまうと、近隣の受験地に振り替えられてしまいます。
2023年度の試験会場でいえば、宮城県の会場で申し込んだのに、実際に受験するのは北海道か埼玉県ということになってしまいます。日帰りで受験できるはずが、1泊する必要が生じますし、交通費や宿泊施設の予約なども必要になってしまいます。
こうしたことが起こらないようにするためには、早めの申し込みが吉ということになります。
万が一申込書類に不備があった場合にも再提出が可能
社労士試験の申し込みに当たっては、受験申込書以外に顔写真や受験資格証明書の提出が必要です。
郵送申し込みでも、インターネット申し込みでも、こうした書類の一部にでも不備があれば受験申し込みは受け付けられません。
受け付けられないといっても、基本的には試験を実施する側から再提出が求められるという形になります。書類に不備があった場合、どの書類のどの部分に不備があるかの連絡が届き、その部分を修正して提出すれば、受験申し込みは認められます。
とはいえ、受験申し込み期間ギリギリに提出してしまうと、修正のうえ再提出の時間が限られてしまい、最終的に受け付けに間に合わない可能性があります。
早めに申し込んでおけば、こうした万が一の事態でも十分に対応する時間が持てますので安心です。
早めに終わらせておけば申し込み後も勉強に集中できる
社労士試験の受験申し込みにはある程度の手間がかかります。顔写真の用意や受験資格証明書の準備など、1日で完了できないケースもあるかと思います。
こうした準備を後回しにすると、受験勉強にも影響がでる可能性があります。
早めに受験申し込みを完了しておけば、そこから試験日まで改めて集中して勉強ができるでしょう。試験直前は受験勉強の中でも重要な時期。直前の追い込みに集中できるよう、早めに申し込みを終わらせておきましょう。
まとめ
社労士試験の申し込みに関しては、郵送申し込みとインターネット申し込みの2つの方法があります。
恐らく2024年度試験においても、この2つの方法での申し込みが可能になるかと思いますが、将来的にはインターネット申し込みのみのなることが予想されています。
これから社労士試験の受験を考えている方は、インターネット申し込みの方法に注目して覚えておくようにしましょう。
それぞれの申し込み方法には、いくつか注意点がありますので、ミスがないよう慎重に手続きを進めるようにしてください。
社労士の最短合格なら通信講座がおすすめ!
難易度の高い社労士試験に最短で合格するためには、通信講座が最適な学習方法です。その理由は以下の通りです。
①忙しくても自分のペースで勉強ができる。
通信講座の利点は、場所や時間を問わず、いつでもどこでも学習が可能な点です。通勤・通学の時間だけでなく、自宅での家事の合間や職場の昼休みなど、さまざまなシーンで勉強できます。仕事や家事、育児で忙しい人も、それぞれの生活リズムに合わせて、自分のペースで学習を進めることができます。
②費用が抑えられる
通学講座の場合、授業料に加えて通学のための交通費も発生します。しかし、通信講座なら受講料がリーズナブルで、交通費もかかりません。
③サポート体制が充実している
市販のテキストを使って独学で勉強する場合、疑問点を自力で解決しなければなりません。それに対して、通信講座では質問対応など学習中のサポート体制が充実しているため、不明点をそのままにせず、安心して勉強を続けることができます。
フォーサイトの社労士通信講座の特徴は?
ここでは、高い合格率を誇るフォーサイトの社労士通信講座の特徴についてご紹介します。
➀わずか5ヶ月での合格実績あり!
通常、社労士試験の合格には約12ヶ月の準備期間が必要ですが、フォーサイトのコースを受講することで、5ヶ月で合格することが可能です。この短期間での合格を実現できるのは、フォーサイトが合格点に特化した教材を提供しているためです。
②試験に不合格でも
受講料は全額返金保証されているため、安心して挑戦することができます。
③満足度90%以上を誇るフォーサイトのフルカラーテキスト
試験に必要な情報量が充実しており、重要な情報はカラーで強調されています。さらに、理解を深めるためのイラストも豊富に含まれており、これが高い合格率に結びついています!
④ フォーサイトが誇る社労士講座の講師陣
フォーサイトの社労士講座は、二神大貴講師、松尾歩美講師、小野賢一講師、加藤光大講師の4名が担当しています。豊富な経験を持つ専任講師が、カリキュラムに沿った講義や教材の執筆を行っています。
⑤「eライブスタディ」は、通信講座でありながら定期的にライブ配信される講義です。
この方式を採用することで、通信講座でも一人で学習する際にペースを落とすことなく、計画的に進めるためのサポートを受けられます。
社労士通信講座の魅力を体験するために、ぜひ資料を請求してください!
通信講座を初めて利用する方や、過去に挑戦して挫折した経験がある方にとって、再挑戦には大きな不安が伴うかもしれません。そんな不安を解消するための第一歩として、無料の資料請求から始めてみるのがおすすめです。
資料請求をすることで、以下のような体験ができます。
➀教材のサンプルや問題集を確認することで、実際の教材の内容を体験し、その理解のしやすさや学習のしやすさを評価することができます。
②無料でeラーニングを試せます。 この機会に、スマートフォン一台で時間や場所を問わず学習できる便利さを実感してください。
③ 社労士試験に最短で合格するためのノウハウ書がプレゼントされます。
1分で完了!
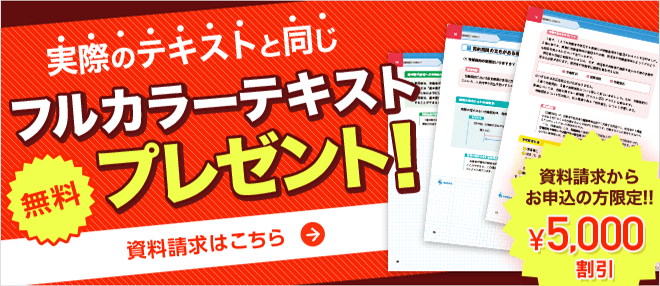
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




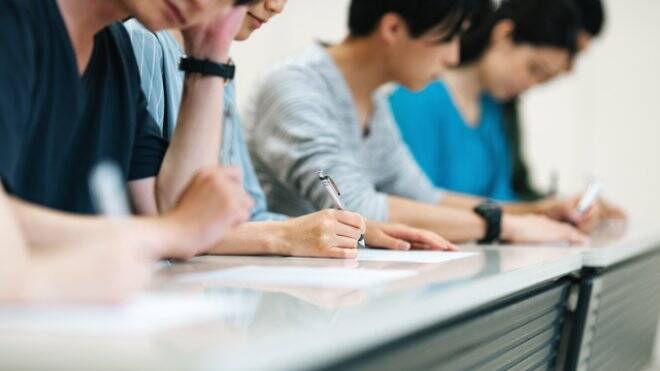


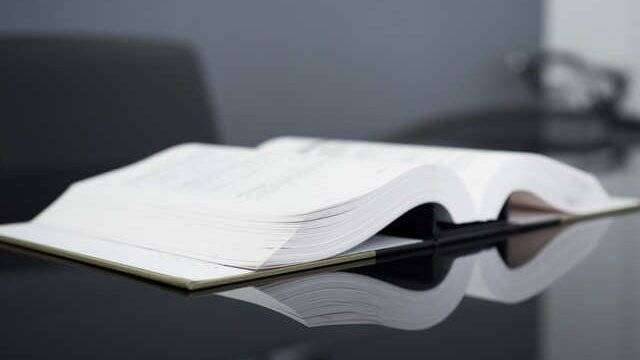









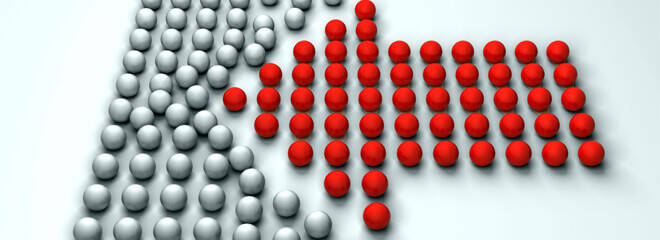
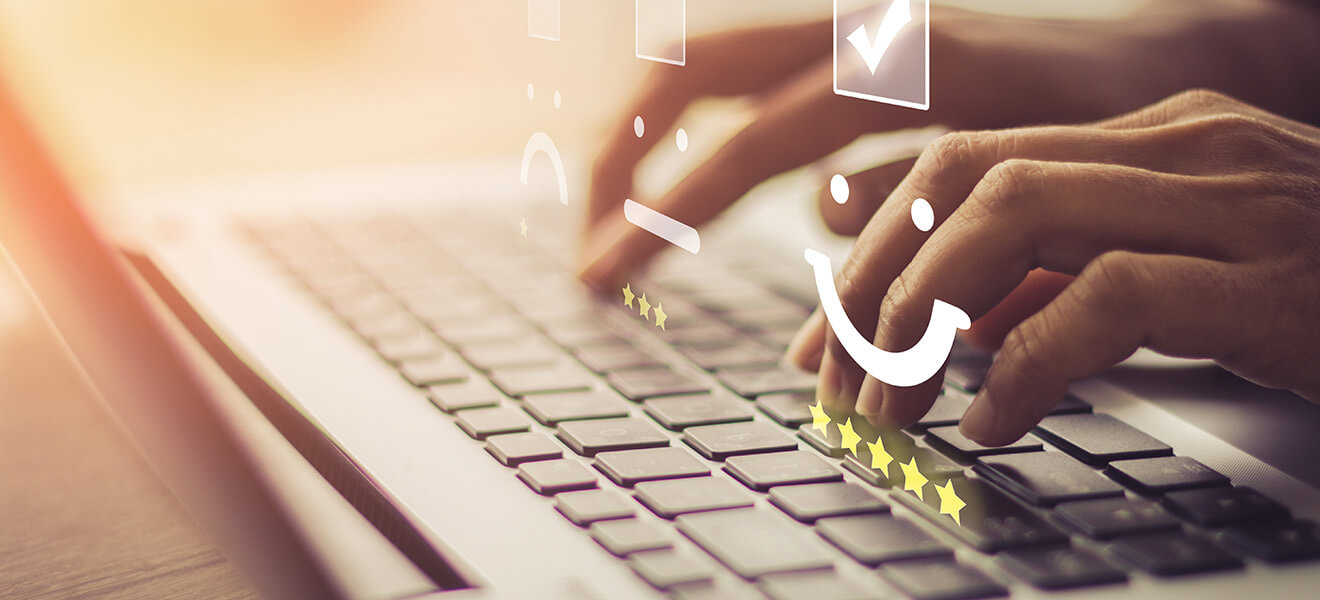





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


