社労士の営業方法、ツールや代行を知る!営業しないという選択も?
更新日:2020年9月29日

社労士受験生の中には、「社労士の資格さえ取得できれば仕事につながる」と考える方も少なくないようです。しかしながら、実際のところは「社労士」の看板を掲げただけで自動的に仕事が舞い込んでくる、というわけではありません。
社労士として活躍するためには、「仕事を獲得すること」という最初の仕事を成功させる必要があります。このページでは、社労士の営業方法について知り、いかに効果的かつ効率的に仕事を得るかに目を向けてみましょう。
フォーサイト小野賢一のご紹介
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう。そうすることで、少しずつ実力が身につきます。
社労士試験に合格することで、「なりたい自分」になれます。「なりたい自分」をめざして頑張りましょう!
社労士の営業方法、先輩はどうしてる?
ひと口に「社労士の営業方法」といっても、様々な手段があり、どのように取り組むかは人それぞれです。ここでは、社労士の典型的な営業方法である「ホームページ」「SNS」「セミナー」について解説しましょう。
併せて、「社労士営業の代行サービス」活用の是非や、電話やFAX、飛び込みといった昔ながらの営業方法の可能性についても触れていきます。
社労士営業の王道「ホームページでの集客」
社労士として開業したら、大半の社労士がホームページを開設し、事務所をアピールします。「ホームページを作ればそこから集客につながるはず」と考える方も多いようです。
しかし、実際のところはそう簡単ではなく、必ずしもホームページが社労士の営業ツールとして役立ってくれるわけではありません。そこで求められるのが、「ホームページの作り込み」です。
具体的には、検索キーワードでヒットしやすくなるようSEOを意識したり、有益な情報発信をしたり等の工夫が求められます。社労士でSEOに精通している方というのはごく少数であるため、士業のホームページ作成代行を専門とする業者が存在します。ホームページを社労士の営業方法として成立させるためには、それなりの知識やノウハウ、または投資が必要になると考えて良いでしょう。
参考:社労士営業から3ヶ月で仕事が取れるプロのwebマーケターに!|WEBMARKS今どきの社労士営業「SNSで情報発信」
最近では、民間企業の営業活動でSNSを活用するケースが増加傾向にありますが、社労士営業においても例外ではないようです。例えば、フェイスブックやインスタグラム、ツイッター等で有益な情報発信をすることで、社労士として注目を集められる可能性があります。
若年層に対して高い訴求効果が期待できるSNSは、若手起業家への営業方法として有効です。とりわけ、社労士は年齢層の高い業界ですから、SNSを用いた社労士の営業方法を積極的に取り入れている実務家はまだまだ少ないのが現状。
そのために、若年層での効果的な集客、他の社労士との差別化のために、SNSを活用する若手社労士が現れ始めているようです。
「セミナー開催」も重要な社労士営業方法
ご自身の専門分野を効果的にアピールし、集客につなげたい場合、社労士としてセミナーを主催する営業方法が効果的です。セミナー参加者はすでにその分野の話に関心がある方ばかりですから、高い専門性を訴えることができれば、スムーズに顧客獲得につながります。
ただし、セミナーを用いた社労士営業では、人前で堂々と話す技術が求められますが、この点がネックとなる方が少なくないと思います。また、当然のことながら、セミナー開催以前に集客のための営業活動をしなければならないことも忘れてはなりません。
番外編①:社労士の営業代行は使い方次第
一般的に、社労士になる方は事務方出身者が多いため、営業活動に不慣れであり、ノウハウにも乏しいケースが目立ちます。もちろん、社労士の営業方法は努力や工夫によっていくらでも開拓できますが、効果的な集客と本業専念を考える上では営業代行等の活用が現実的という考え方もあります。
社労士の営業代行としては、例えば、ホームページ作成代行や士業のマッチングサービス等がありますが、これらを活用する際には必ず費用対効果に目を向ける必要があります。継続的に支払うことになる営業代行費用を考慮しても利益を見込むことができるのか、この点はビジネスを展開する上で重要な視点となります。
営業代行自体は社労士にとって有益なサービスといえますが、社労士自身のプラスにつながるよう上手く活用できなければ、総合的に見てコストばかりがかさむ結果につながることもあります。
番外編②:FAXや電話、飛び込みでの社労士営業はどうなのか?
さて、営業活動といえば、FAXや電話、飛び込みといった方法が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか?
社労士の営業方法としても、最近でこそウェブを活用した取り組みが増加傾向にありますが、ひと昔前まではこれらの手段が主流でした。そして、数ある士業の中でも比較的年齢層の高い社労士業界では、まだまだ昔ながらの営業活動を実践し、一定の効果をあげている実務家もいます。
FAXや電話、飛び込み等は現代でこそ「時代錯誤」と揶揄されることも少なくありませんが、営業方法自体は決して否定されるべきものではありません。重要なのは、各人が取り組みやすい方法で、ストレスなく仕事を得られることですから、営業方法の選択肢のひとつとして、必要に応じて活用できるのが理想的です。
社労士は「営業活動しない」の声も
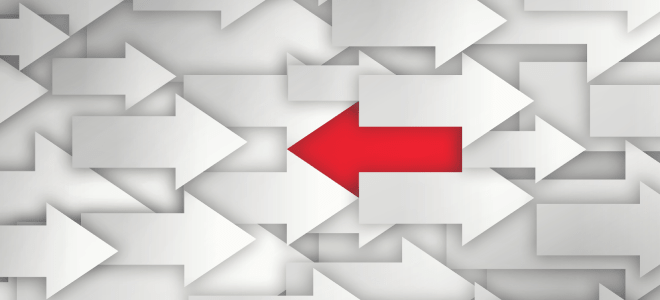
ここまでは、「社労士の営業方法」についてご紹介しました。社労士であるからといって自動的に仕事が舞い込んでくるわけではない以上、営業活動への努力を欠かすことはできませんが、一方で、「士業たるもの営業活動をするべきではない」という意見を耳にすることもあります。
ここでは「社労士であれば営業活動をしない」の真意について、考えてみましょう。
社労士は「営業活動しない」の理由① 営業活動は価格競争の引き金となるから
社労士は営業活動すべきではない第一の理由として、「仕事の安売りを避けるため」が挙げられます。社労士が積極的に営業活動することで、「顧客目線での比較検討」において勝負せざるを得なくなります。
比較検討のための要素には様々ありますが、やはり「金額」で比べられることは多く、そうなればどうしても価格競争は避けられません。価格競争が一般的になると、社労士であっても薄利多売に陥りがちになり、結果として仕事の質の低下を招くことになります。
社労士の地位と名誉を鑑みれば、こうした事態はあってはならないことです。
社労士は「営業活動しない」の理由② 方法を間違えれば士業のブランドイメージ低下を招くから
社労士の営業活動によって悪影響が及ぶ可能性があるのは、社労士報酬だけでなく、社労士としてのブランドイメージについても同様です。
営業活動といえば、多少なりとも顧客に対しへりくだる姿勢が求められますが、本来顧客を導く役割を担うべき社労士が下手に出て行う営業は、社労士のブランディングを考える上で好ましいものではありません。
社労士は「営業活動しない」の理由③ そもそも事務方出身者が多く、営業が苦手な社労士が多いから
さらに、社労士は「営業活動をしない」のではなく「できない」という見方もあります。既にこのページでも触れている通り、社労士になる方には事務職出身者が圧倒的に多く、総じて保守的な傾向にあります。
もともと営業職をバリバリこなすような、前面に出ていくタイプではないため、開業しても上手く営業活動に取り組めないケースは珍しくありません。
もちろん、苦手意識の克服や営業スキルの向上は、社労士開業後に培うことができますから、まずは自分自身に対する「営業は無理なんだ」というレッテルをはがし、前向きに理業活動に取り組む姿勢が求められます。
社労士営業は「売り込み」ではなく「サポート」のイメージで行うべし

仕事を得るためには、社労士であっても営業活動に取り組む必要があります。ところが一方で、営業方法に工夫を凝らさなければ、社労士の営業活動はかえってマイナスに働いてしまう可能性があるため、注意が必要です。
例えば、前述の通り、「売り込み」として社労士の営業に取り組むことは、仕事の質や社労士の地位を考える上では適切とはいえません。また、「営業」を意識しすぎるあまり、苦手意識で上手くいかなくなる社労士は少なくありません。
それでは、社労士はどんな営業方法に目を向ければ良いのでしょうか?その答えは、ガツガツ前のめりになって売り込むようなやり方ではなく、「サポート」に主軸を置いた営業にあります。
社労士になる人の性質や社労士としてのブランドイメージを考慮すれば、顧客を悩み相談に乗り、解消してあげるイメージで営業を行えるのが理想的な姿といえるのではないでしょうか?
社労士講座に最短合格しりなら通信講座がベスト
難易度の高い社労士試験を最も効率的に突破する方法は通信講座の利用です。その理由を具体的に説明します。
➀過密スケジュールでも、自分のペースで学べる
通信講座なら、場所や時間にとらわれず、いつでもどこでも学習できます。移動中や家事の合間、仕事の休憩時間にも勉強を進められます。どんなに忙しい人でも、自分の生活リズムに合わせて学習を続けられます。
②費用面での利点があります。
通学講座は授業料に加えて交通費もかかりますが、通信講座を利用すれば、受講料が比較的安く、交通費を気にする必要もありません。
③サポート体制の面で優れています。
独学での勉強では解決が難しい疑問点も、通信講座ではサポート体制がしっかりと整っているため、気軽に質問でき、スムーズに勉強を続けることが可能です。不安を感じることなく学びを深めることができます。
まとめ
- 社労士は、資格さえ取得すれば仕事につながるわけではなく、営業活動を成功させることで初めて活躍の道が開かれます
- 社労士の典型的な営業方法には「ホームページ」「SNS」「セミナー」がありますが、いずれも本人の得手・不得手による部分があることに加え、集客につなげるための工夫やノウハウ、努力が不可欠です
- ひと口に「社労士の営業方法」といっても、昔ながらのFAXや電話、飛び込み営業の他、最近主流のウェブを用いたものなど手段は様々ですが、自分に合った、取り組みやすい方法で取り組めるのが理想的です
- 「安易な価格競争やブランドイメージの低下を避けるべき」「そもそも営業に不慣れな人が多い」等の理由から、社労士の営業活動をあえてしないという考え方もあります
- 社労士の営業を考える上では、ガツガツと売り込むような方法ではなく、顧客の悩み解消に向けたサポートに徹するやり方に目を向けるのが望ましいといえます
1分で完了!
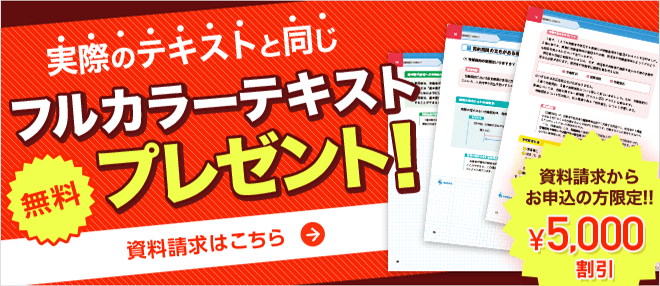
小野賢一(おの けんいち)
「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師




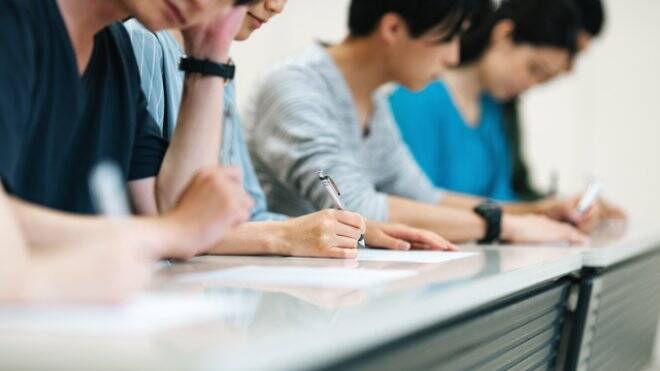


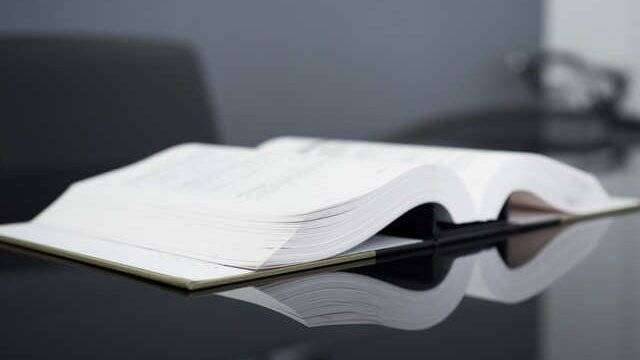









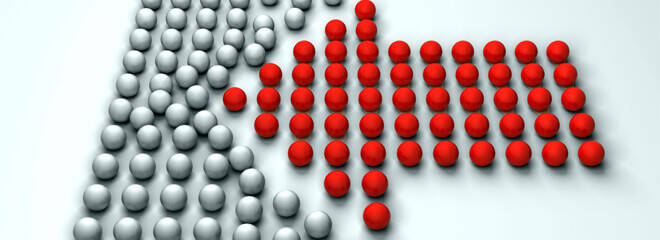
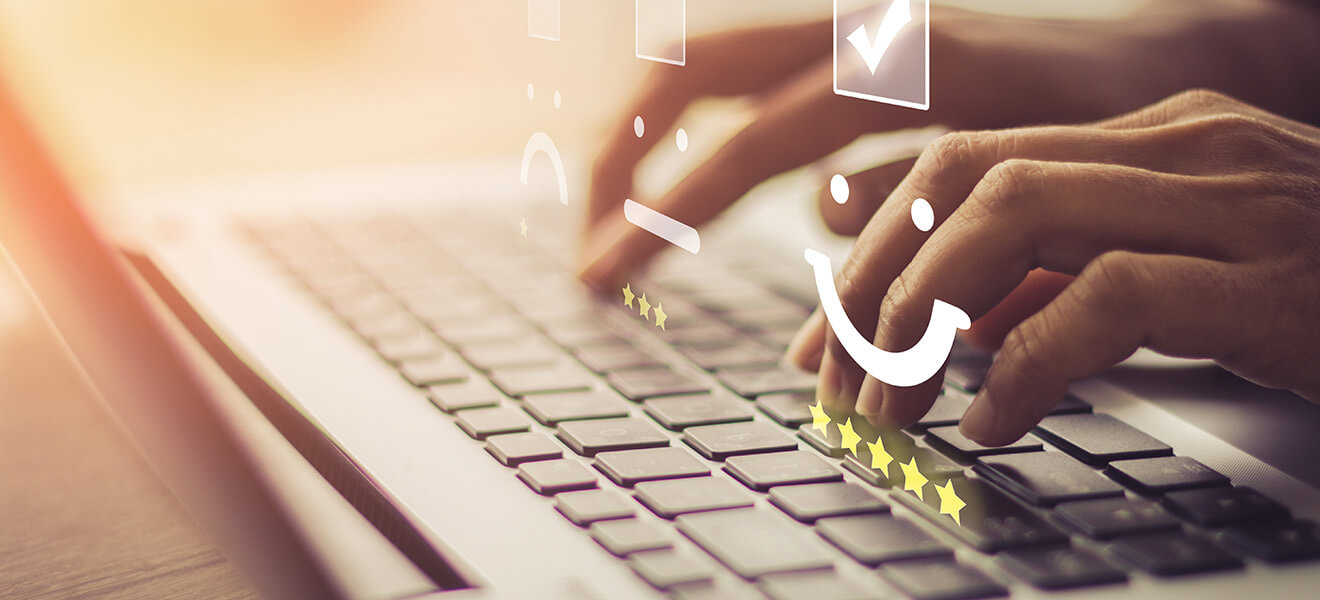





 ログイン
ログイン



 0120-966-883
0120-966-883


