宅建士の年収はいくら?働き方などの条件別の事例から年収の上げ方まで解説
更新日:2024年6月14日
「宅建(宅地建物取引士)」の資格を活かして働いたら、どのくらいの年収を見込めるものなのか気になっている人も多いでしょう。一口に宅建士と言っても、企業に勤務する場合と、独立開業する場合とでは年収が異なります。
この記事では、宅建士の「平均年収」や「働き方による年収の違い」「年齢別の年収」「地域別の年収」など、年収にまつわる情報を最新データに基づき、様々な観点からわかりやすく紹介します。 また、宅建士として活躍する中でより高収入を目指す方法や、宅建士の仕事について、そもそもどうすれば宅建士になれるのか、といったことに関しても解説します。不動産業界への就職・転職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 企業に勤務している宅建士の平均年収は500万円~600万円程度。
- 努力次第で1000万円越えの年収を稼ぐことも夢ではありません。
- 宅建士の年収は年齢によって差があり、一般的に20代から50代まで、段階的に上がっていく傾向にあります。
- 宅建士の資格を取得すると、年収アップを目指せる、就職・転職に役立つなどのメリットがあります。
- 宅建士として、より高収入を得るためには、「営業で数字を上げる」「大手企業で管理職を目指す」といった方法があります。
- 宅建に挑戦したいけれど、自信がないという人に試してほしいのがフォーサイトの通信講座です。
フォーサイト窪田義幸のご紹介
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします。そのために全力で指導します。
宅建に合格すると人生が変わります。合格まで一緒に頑張りましょう!
宅建士(宅地建物取引士)の平均年収

宅建士(宅地建物取引士)の年収は500~600万円前後です。日本の平均年収が458万円(国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)であることから考えると平均より高めになります。その理由として挙げられるのは、不動産業界が常に宅建士を必要としていることや、宅建士にしかできない業務があることなどです。
ただし、経験とキャリアを重視する業界なので、最初から500~600万円というわけではありません。近年の求人情報を集計すると、入社直後の宅建士の年収は、会社の規模や地域、本人の経験によって差はあるものの、300~400万円が平均的なラインと言えます。
企業に勤務している宅建士(宅地建物取引士)の年収
企業に勤務している宅建士の平均年収は、原則通り500万円~600万円程度と考えるのが適切です。とはいえ、勤務先の会社の規模や従事する業務、役職、給与形態(歩合給か固定給か、諸手当の有無)等によって差が生じることもあるでしょう。
一般的には、大企業勤務で働く宅建士の年収は600万円程度と相場を上回るケースが想定されます。一方、中小企業の宅建士の年収は500万円程度と言われています。事務作業のみを行う場合は300万円程度から、不動産全般の業務をしているなら550万円程度になるなど、年収は業務内容によっても変わります。 なお、企業規模を問わず、膨大な業務量により長時間労働となれば、時間外・休日労働手当の支給によって年収は高くなります。
宅建士(宅地建物取引士)の働き方による年収の違い
一口に宅建士(宅地建物取引士)と言っても、独立開業している場合と、会社勤めをしている人の場合とでは年収が変わってきます。
独立開業している宅建士の年収相場は、独立直後だと200万円~300万円程度のこともあり、一概には言えません。でも、仲介手数料などを全て自分で得られるので、人によっては1000万円以上稼いでいます。会社勤めをしている宅建士の年収相場は500~600万円前後。年収の内訳は以下のようになります。
| 年収 | 300万円 | 450万円 | 500万円 | 650万円 |
|---|---|---|---|---|
| ボーナス | 約48万円 | 約72万円 | 約80万円 | 約104万円 |
| 月額給与 | 約17万円 | 約25万円 | 約28万円 | 約36万円 |
独立している宅建士(宅地建物取引士)の年収
独立開業した宅建士の年収は、営業努力や同業他社との差別化、働き方等により人それぞれです。また、企業に勤務する宅建士と違って、事務所の賃料や事業運営のための経費を自身で負担するので、平均的な収入の想定は難しくなります。
とはいえ、仕事柄、広い事務所や多数の従業員を確保する必要はなく、在庫を抱えることもありません。独立開業した宅建士の中には、経費を抑えつつ、企業勤務の宅建士以上に稼ぐ人も少なからずいるようです。独立直後の年収は200~300万円程度が多いのですが、実力のある人なら初年度から高額な収入を得ることも可能です。一般的な年収は400万円前後と言われていますが、努力次第で1000万円超えの年収を稼ぐことも夢ではありません。
条件別宅建士(宅地建物取引士)の平均年収
キャリアや経験、業務内容、労働時間などによって収入に差が出るのはもちろんですが、宅建士の年収は年齢や性別、地域によってもずいぶん変わってきます。
ここでは、年齢別(20代~60代)、性別(男性・女性)、地域(働く場所)別といった条件に分けて、それぞれ、どれくらい平均年収が変わるのか、ということについて詳しく説明します。ご自身がどの条件に当てはまっているのかを考えながら読み進めることをおすすめします。
【男女別】宅建士(宅地建物取引士)の年収
企業で働く宅建士の平均年収は500~600万円ほどと言われていますが、男女別に見ると、女性の年収のほうが男性の年収よりも100万円程低くなるようです。こうした男女の年収差は、単に性別の違いというよりは、資格取得後の働き方の変化によるものと考えられます。
というのも、女性の場合、妊娠・出産をきっかけに非正規雇用に切り替えることが多く、一貫して正社員として働き続けることが多い男性と比べれば、年収が低くなる傾向にあるのです。とはいえ、ライフスタイルが変化しても資格を活かして働ける点には、年収以上の価値があります。また、資格がなければできない業務が多い分、一般的な女性の平均年収(350万円前後)よりも高い収入を得られます。
| 性別 | 平均年収 |
|---|---|
| 男性 | 381万円~713万円 |
| 女性 | 278万円~538万円 |
関連記事:
女性宅建士についての詳細はこちら
【年齢別】宅建士(宅地建物取引士)の年収
宅建士の年収は年齢によって差があり、一般的に20代から50代まで、段階的に上がっていく傾向にあります。特に50代は役職に就く人が増えることにより、平均年収が最も高くなります。60代は定年退職後に嘱託職員として働くなどのケースが多いため、ピークを迎える50代よりも平均年収が下がるようです。
国税庁の年齢別階層年収をもとに、フォーサイトが独自に宅建士の年齢別年収を集計したところ、20代は300万円~380万円、30代は420万円~480万円、40代は500万円~600万円、50代は600万円~650万円、60代は430万円~450万円との結果になりました。
ただし、会社によっては実績に応じたインセンティブを支給している所もあり、中には20代で700万円以上稼ぐ人もいます。
【地域別】宅建士(宅地建物取引士)の年収
他の職業同様、宅建士の平均年収も地域ごとに異なります。全国平均は500万円から600万円ではあるものの、地域によって差が生じます。ただし、実際の年収は企業の規模や、その会社で取り扱う不動産の価格帯等、総じて勤務先に起因する要素が多いので、地域別の平均年収を出すのは難しい、というのが実情です。
そのうえで、あえて平均年収を出すと、最も高いのは東京都の約700万円。次いで大阪府の約650万円、愛知県の約600万円と続きます。反対に年収が低いのは沖縄県や宮崎県、青森県の約430万円です。都市圏のほうが年収は高い傾向にあります。
物価や不動産価格との関わりが深いため、それらに依存しがちな部分も。沖縄県などは中小企業が多い影響で年収が低くなりがちです。
宅建士の仕事とは
宅建士(宅地建物取引士)は、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣や都道府県知事から免許を受けた専門家で、主に不動産取引に関する業務を行います。業務内容は不動産の売買や賃貸に関する契約の仲介、不動産の査定や価格の相談、顧客の要望に応じた物件の探索・提案など、多岐に渡ります。
不動産取引には、法律や契約など複雑な要素が含まれるため、一般の人々にとっては難解な場合があります。そのようなときには、豊富な専門知識や経験を活かして顧客のニーズに応え、スムーズな取引の実現に向けてサポートすることを求められます。
関連記事:
宅建士を取得するメリットや仕事内容についてはこちら
宅建士の資格を取得すると年収が上がる人の特徴
宅建士の資格を取得すると、年収アップを目指せる、就職・転職に役立つなどのメリットがあります。不動産取引では、高額な金銭が動くので、宅建士だけが行うことのできる「独占業務」が定められています。各宅建業者には、従業員の5人に1人以上の割合で宅建士を設置することが義務付けられているため、宅建の資格取得者に資格手当を支給したり、昇給の要件に加えたりして宅建の取得を推進しています。
また、宅建は不動産業界のみならず、金融業界や建築業界でも必要とされています。例えば銀行の融資や建設会社の物件の売買などには宅建士の専門知識や資格が役立ちます。つまり宅建は不動産業以外への就職や転職においてもメリットのある資格なのです。
宅建士(宅地建物取引士)で年収1,000万は可能?
宅建士の仕事で年収1000万円を叶えるのは夢ではありません。企業勤務の宅建士の場合、年収アップのポイントは「大企業に勤めること」「固定給と歩合給の両方でしっかり稼げること」の2点です。これらは簡単なことではなく、キャリアを積み重ねると同時に社内での地位を高めることも大事。地道に努力して、ようやく年収1000万円に到達できるようなイメージです。
一方、独立開業した宅建士は、家業を継いだ二代目社長であれば、年収1000万円超えはそれほど難しくありません。ただし、自分で事業を立ち上げた人の場合は、すぐに年収1000万円を得るのは厳しいでしょう。営業努力や同業他社との差別化に奮闘しながら、徐々に年収アップを目指すことになります。
宅建士の年収の上げ方
宅建士として、より高収入を得るためには、「営業で数字を上げる」「大手企業で管理職を目指す」といった方法があります。不動産業界の営業職は、一般的に歩合制が導入されているので、契約件数を増やせば年収を上げられます。また、大手不動産会社で管理職に就いたら、1000万円近い年収を得られる可能性大です。
キャリアを積み、企業を離れて一人でやっていける自信がある人ならば「独立開業」して稼ぐ方法を選ぶのもおすすめです。
宅建士の年収を上げる方法①:営業で数字を上げる
前述の通り、不動産業の営業職は歩合制が導入されています。営業として地道に契約数を増やせば、年収を上げられるでしょう。契約を取るのは簡単ではありませんが、宅建士としての専門性を活かして成約率を上げることで、年収1000万円超を稼ぐ人もたくさんいます。
歩合制で得られる金額は企業によって異なるため、より年収を上げたいのであれば、歩合給の高い会社を選びましょう。ただし、歩合の割合が高い企業の場合、その分、基本給を抑える傾向が見られます。歩合の割合が高い所や完全歩合制の会社で働く際は、契約が取れなかったら収入を得られないリスクがあることも忘れてはいけません。キャリアを積むまでは固定給が高い会社で働くという手もあります。
宅建士の年収を上げる方法②:大手企業で管理職を目指す
厚生労働省の調査によると、大手不動産取引業で働く、55~59歳の職員の平均年収は966.7万円です。宅建士を取得して仕事上で評価されれば、将来的に高い役職に就き、1000万円近い年収を手にする可能性も開けるでしょう。
ただし、大手企業の管理職のポストは競争率が高いため、高度なスキルと実績を求められます。管理職として権限や責任を持って働くのであれば、日ごろから知識のアップデートが欠かせません。不動産取引に関する法律や、宅建士の業務にまつわるルールは時代の変化に対応して変わっていきます。管理職として優れた判断をするためにも、情報収集を怠らないようにしたいものです。同時に、日々の業務で力を発揮し、キャリアを積むことも重要です。
宅建士の年収を上げる方法③:独立開業する
宅建士として独立した場合、自分で案件を探して取引をするため、会社勤めの間は企業側と分けていた仲介手数料などの収入が全て自分のものになります。ただし、会社の運営にはリスクが伴うことも忘れてはいけません。
独立には、事務所を構えるための初期費用やホームページ制作などの宣伝費、固定費をはじめとした維持費がかかります。事業を軌道に乗せるためには、営業スキルは当然のこと、不動産に関する情報の収集や、同業者とのネットワークも重要になってきます。 高収入狙いで早い段階から独立に踏み切るのもいいけれど、まずは会社勤めをして宅建士としての実績を作り、一人でもやっていけるという自信がついてから独立開業するといいでしょう。
宅建士になるには

宅建士になるには、まず、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣や都道府県知事からの免許を受けるための「宅地建物取引士資格試験」に合格する必要があります。年に一度の試験に合格したら、実務経験や所定の研修の受講などの条件を満たしたうえで、都道府県知事に申請して正式登録を受けると、宅建士証を交付され、資格証明として扱えます。この資格があれば、宅建士としての業務を始められ、独占業務も担えるのです。
宅建士試験に最短合格したいなら通信講座がベスト
高難度の宅建士試験に短期間で合格したい人には、通信講座をおすすめします。この方法が優れている理由は以下の3つです。
①生活に合わせて自分のペースで勉強できる
スマホやタブレットで始められる通信講座なら、時間や場所を問わずにアクセスできるので、通勤・通学の時間、家事の合い間、昼休みなど、スキマ時間に学習を進められます。毎日忙しく過ごしていても、個々のスケジュールに合わせて勉強できるでしょう。
②コストパフォーマンスがいい!
予備校など、通学するタイプの講座の場合、授業料のほか、交通費もかかるので大変です。その点、通信講座なら受講料がリーズナブルで、交通費用も節約できます。
③充実した学習支援が魅力
独学だと解決できないような疑問も、通信講座ならば専門家に質問できるなど、不明点をなくすためのサポート体制が充実しています。そのため、学習する中で感じる不安が解消され、より効率的に学習を進めることができるのです。
フォーサイトの宅建士通信講座の魅力とは?
宅建に挑戦したいけれど、自信がないという人に試してほしいのがフォーサイトの通信講座です。その理由を紹介します。
①4ヶ月で合格可能
一般的に宅建士試験には1年の学習を要しますが、フォーサイトの講座なら、4ヶ月で合格する方も。これは、満点ではなく合格点を取ることに焦点を当てたフォーサイト合格メソッド満載の教材で学んだからです。
②仮に不合格でも
残念な結果に終わっても受講料を全額返金されるので、リスクなしで勉強に専念できます。
③満足度抜群のテキスト
試験に必要な情報をカバーしたテキストは、フルカラーでイラスト満載。理解しやすく高い合格率を支えています。
④講師歴20年以上の講師陣
これまでの経験と専門性を活かして価値ある講義と教材を提供しています。
⑤「eライブスタディ」
定期的に配信されるライブ形式の講義を見ると、独学でもペースを落とすことなく計画的に学び続けられます。
宅建士通信講座を体感するなら資料請求しよう!
これまで通信講座を受けたことがない方、過去に通信講座を受講してみたけれど挫折した経験があるという方は、新たに通信講座を始めたいと思っても不安が大きく、なかなか一歩を踏み出せなかったりするでしょう。そんなときはまず、資料請求をおすすめします。無料で申し込め、次のような体験が可能となります。
①テキストや問題集をチェックできる
実際の通信講座で教材として使用されているテキストのサンプルや問題集を見ることができます。目を通すことで、どれほどわかりやすく、学習しやすいか、といった点を実感できるので、講座を受け始めた後の自分の姿をしっかりとイメージできるでしょう。
②無料でeラーニング体験が可能
スマートフォンがあれば、時間や場所を選ばずにいつでもどこでも学習できるeラーニング講座を無料で視聴できます。その便利さや気軽に学べる楽しさを、身をもって体感できるチャンスです。
③宅建合格のノウハウを詰め込んだ本を進呈
宅建士試験に合格するためのノウハウを教えてくれる、フォーサイトのオリジナル書籍を特別にプレゼントします。フォーサイトが20年以上かけて築いてきた「フォーサイト合格メソッド」に触れることで、学習へのモチベーションが上がって合格モードに切り替わり、最大限のパフォーマンスを発揮できるようになるはずです。効率良く学び、できるだけ早く宅建試験に合格するためにも、成果の出やすい勉強法を身につけましょう。
年収アップに役立つ宅建合格を目指すなら通信講座がおすすめ
宅建は不動産業界で働く場合のみならず、他業界への転職や年収アップにも役立つ資格です。努力次第で1000万超の年収を狙うこともできるので、武器の一つとして、ぜひ取得したいものですよね。
とはいえ、誰でも簡単に合格できるわけではないため、効率良く勉強することが重要。早めに目標を達成したいなら、4ヶ月での合格も可能なフォーサイトの通信講座をおすすめします。フォーサイト合格メソッドを身につけ、明るい未来への切符を手に入れましょう。
1分で完了!

窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
●フォーサイト講師ブログ



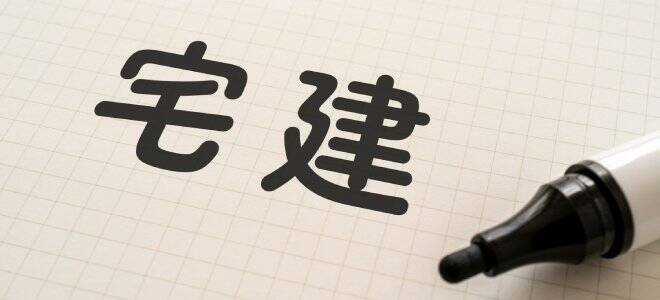











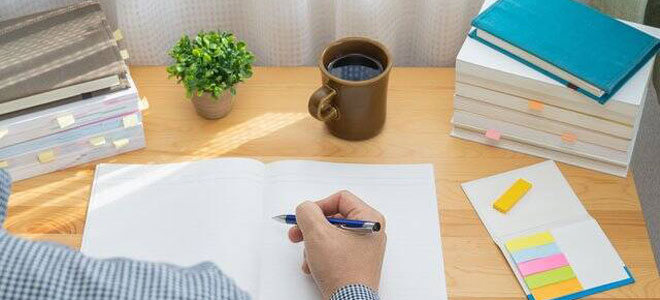

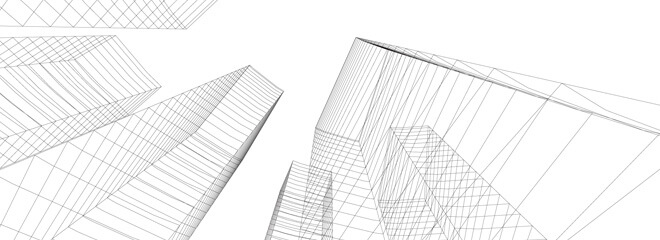





 ログイン
ログイン




 0120-966-883
0120-966-883


